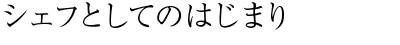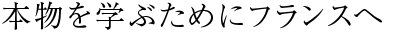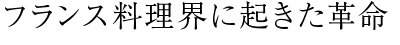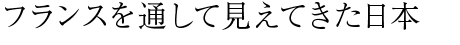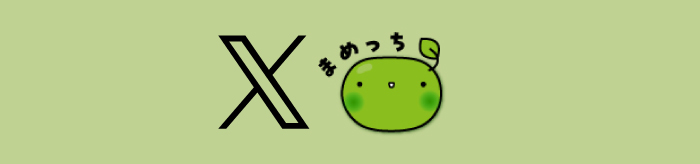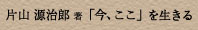フランス料理の歴史と新しい風”クラシカル・モダン”
1970年頃のフランス料理界は、それまでオーギュスト・エスコフィエが中心となって確立していたクラシックなスタイルから、ヌーベルキュイジーヌという新しいスタイルへの端境期にありました。 そんな時代に、パリの三ツ星レストランなどで修行を積み、その後、日本のフランス料理に様々な新しい息吹をもたらした横田オーナーシェフ。数々のホテルで総料理長を歴任し、シェフ、料理顧問、経営者として、今もなお新しいフランス料理のかたちを探求し続ける姿は、多くの日本人シェフに影響を与えています。


1947年 岡山生まれ
新大阪ホテル(現リーガロイヤルホテル大阪)に入社後、単身渡仏。パリの三ツ星レストランなどで学び、帰国後は、大阪ホテルプラザ「ル・ランデブー」のシェフ、大阪全日空ホテル「ローズルーム」シェフ兼総料理長、ANAインターコンチネンタルホテル東京洋食総料理長を歴任。 1997年パリ「ジョルジュ・サンク」にて日本人初となる自身のフェアを開催。2006年には、フランス共和国農事功労章シュバリエを受章。現在は、トックブランシュ国際倶楽部理事、ANA料理アドバイザー、企業コンサルタントを務められ、2009年6月より「ル・ヴァンサンク」オーナーシェフに就任。2013年4月には岡山県倉敷市に「カフェレストラン ヴァンサンク」を新たに開業されました。
私は幼い頃から野球をやっていまして、倉敷工業という当時の野球の名門校と言われた高校に入学しました。そこには、県下の優秀な選手が沢山集まって来ていましてね。1年くらい経って自分なりにこれからの道というものを考えた時、このまま続けても中途半端であると思って、野球選手への道を断念することにしたんです。その後、食べることも料理を作ることも好きだったので、料理人を目指そうと思いました。体力には自信がありましたし、ずっと運動部でしたからしつけの厳しい世界にも適応出来るだろうと考えたのです。
料理人になろうと決意した私は、やるからには一番を目指そうと思い、「帝国ホテルに入って、料理人になろう。」と、漠然とですがそれを目標にしました。ただ、当時は周りにそのような情報も人脈も何もない状態でしたから、模索する日々がしばらく続きました。そんな中、倉敷の国際ホテルにご縁があって、当時の総支配人に料理界を目指しているという話をさせてもらったとき、帝国ホテルも良いけれど新大阪ホテル※1はどうかと言われました。当時、その二つのホテルは「東の帝国、西の新大阪」と賞されていたのです。それで、その総支配人のご紹介で新大阪ホテルに入れていただくことができました。
※1 新大阪ホテル・・・現在のリーガロイヤルホテルの前身。1935年(昭和10年)に竣工。
料理人になろうと思った当初は、フランス料理がどういうものであるのかさえ知りませんでした。しかし、幼い頃からジャズや洋楽など、洋文化に触れながら育ったこともあって、おしゃれな料理=フランス料理という感覚があったのです。それで、とりあえずホテルに行けばフランス料理に出会えるだろうと思いましてね(笑)。最初は単純な動機だったかも知れません。
ホテルのレストランでの仕事は、初めはパントリー(主に配膳係り)や紅茶を入れるセクションに入ります。やり方は「on the job」。つまり、実体験を通して覚えていくのです。ですから、紅茶やコーヒーのいれ方であったり、食パンを同じ厚さできっちり切り分けたりなど、厳しく教えられましたのでよく覚えています。
それから、2年目になるとストーブ前(温かい料理の担当)、コール場(冷たい料理の担当)、ブッチャー(下ごしらえする担当)と、それぞれのセクションに分かれていきました。そこはホテルのメイン・ダイニングでしたから朝食、ランチ、ディナー、宴会場に至るまで経験している内に、全てを覚えていくまうことも多くありました。ですから、いつのまにかのです。その内、時代の流れと共に新しいホテルがどんどんオープンし、我々の世代より上の優秀な先輩方はそちらへ行ってし3年程の経験しかない我々が現場を取り仕切ってやっていました。もちろん、その経験は深くはありませんが、メイン・ダイニングでやることはどうにかこなすことが出来たのです。

・ フラン…卵や牛乳などを混ぜた液体をもとに、加熱して固めた料理。
・ ブリック…薄いクレープ状の皮のこと。

自分たちがメインで料理をするようになるにつれ、私は本場に行ってフランス料理をもっと学びたいという気持ちが強くなっていました。当時、フランスのキッチンには必ずと言って良いほどあった「レ・ペルトワール※2」という本の原書を本場から取り寄せ、辞書を片手に解読していく内に、我々が日本でやっているフランス料理のその奥には、とんでもなく深いものがある事を知ったのです。
※2 レ・ペルトワール・・・オーギュスト・エスコフィエが著した5000種類以上にも及ぶ料理本「ル・ギード・キュリネール」を、氏の弟子たちが簡素化してまとめた料理手帳。
私はその本の内容に触発され、フランスへ行くことを決意しました。当時、私が頂いた初任給は1万円5千円程で、フランスへ行く飛行機代が24万数千円という時代でした。それも片道。その頃のフランスへの交通手段は他に船や鉄道もありました。ある時、フランスからの船が神戸へ寄ることを知って、フランスの匂いを嗅ごうと神戸まで行ったことがあります。船からフランス帰りの人が降りて来ると、何となくフランスの雰囲気を味わえたような気がしました。そんな単純な憧れを持っていましたね。
もちろん、フランスには人脈がありませんでしたから、行く前に出来る限りのコネクションを作っておかなければと思っていました。そこで、当時フランスへの研修経験があった先輩に紹介状を書いて頂いたり、フランス語を習いに行っていたのでフランス人講師に相談したりしたんです。そうしたら彼に、向こうに行けば何万軒もフランス料理のお店があるからどうにかなると言われましてね(笑)。私もとりあえず行って、ダメなら帰るしかないなと思っていました。
結局、フランスへは一番早い飛行機を選び、18時間くらいかかって行きました。それから、毎日仕事を探す日々が始まります。目指すお店はいわゆる高級店でしたので、とにかくそういうお店に行くのですが当然断られます。シェフに会うためには11時、14時半、18時頃が休憩や手が空きやすい時間で、この3回、つまり一日に回れるお店は3店舗しかないのです。それを何度も繰り返しましたね。
そうこうしながら、講師の実家の住所を教えてもらっていたので、行くことにしたんです。実家があるのは、パリから150キロほど離れたノルマンディのリルボンという小さな町で、そこまで行くのは本当に大変でした。行って驚いたのは、彼の実家がお城だったんです。1ヶ月くらい滞在させて頂いたんですが、お礼としてやることと言えば広い庭の草を刈ることくらいでした(笑)。
その後、彼のお父さんの紹介で避暑地として有名なエトルタという街のレストランに就職させてもらうことができ、そこのオーナーにとても気に入ってもらいましてね。でも、次の問題はビザが取れないことでした。就労ビザというのは今でもそうですが、取得が大変難しいのです。何度も申請したけれどダメで、仕方なくまたパリに戻ることになりました。その後、1年間の研修ビザが下り、エッフェル塔にあるレストラン「ジュール・ベルヌ」で働くことになったんですが、研修ビザは1年間で申請は1度しか出来ないんです。それでまたビザが切れる頃になって、そのお店のオーナーに尽力してもらって何とか正式なビザが下りることになりましてね。やっとどこでも働けるようになり、フランス人と同じ待遇で雇って貰えるようになりました。それまでは本当に落ち着かない日々でしたね。

・ セップ茸…ヤマドリタケ。イタリアのポルチーニと同種のキノコ。
・ パピヨット…包み焼き料理。

パリでは、ビザを取得してくれた「ジュール・ベルヌ」の他に、コンコルド広場にある「ホテル・ドゥ・クリヨン」や「マキシム」などでも働きました。当時、若い人達は同じところに長くいないことが多いのですが、私はクリオンに3年程いました。
その当時の時代背景を話しますと、ちょうど1970年頃というのはフランス料理の中でクラシックなものと新しいものとの端境期でした。その頃、クラシックを代表していたのは、「オーギュスト・エスコフィエ(1846年-1935年)」というホテル・リッツやロンドンのカールトン・ホテルの総料理長を歴任した人で、そのエスコフィエの作り出した料理がその頃のクラシックなフランス料理の中心になっていたのです。そんな時代の中で新しく生まれようとしていたのが「ヌーベルキュイジーヌ(新しい料理という意味)」というスタイル。これは地産地消であったり、運送手段の発達によって海産物の美味しいものや鮮度の良いものが簡単に入手できるようになって、そこにあまり火を加えずフレッシュな状態で出せるようになったりと、時代の流れによる変化から生まれました。
このスタイルは、リヨンの郊外にある「ラ・ピラミッド」というレストランから始まります。そこのオーナーシェフが「フェルナン・ポワン(1897年-1955年)※3」という人で、そこで働いていた弟子たちの中から、後にミシュランの三ツ星を総なめにしてしまう、「ポール・ボキューズ※4」や「アラン・シャペル」、「フランソワ・ヴィーズ」、「ルイ・ウーティエ」などが出てきました。そんな新進気鋭のシェフ達がマスコミの力によって世界中に名を知られることになり、ヌーベルキュイジーヌというスタイルは世界中に認知されることになったのです。
そんな時代にフランスでベーシックな料理を学びながら、新しい料理をやりたいと思っていた私は、当時飛ぶ鳥を落とす勢いでフランス料理界を席巻していたポール・ポキューズさんに何度か手紙を書き、一緒に仕事がしたいということを伝えました。しかし、残念ながらフランスにいる間に叶うことはなかったのです。
※3 フェルナン・ポワン・・・20世紀最高のシェフと謳われ、顧客の中には各国の王室、芸術家のピカソやジャン・コクトー、米国大統領のアイゼンハワー、実業家のロックフェラーなどが名を連ねていました。ポワン氏がオーナーシェフを務めた「ラ・ピラミッド」は1933年から1986年まで(ポワン氏が亡くなった1955年以後はポワン氏の夫人が引き継ぎ)、ミシュランの三ツ星を守り続けたレストランです。
※4 ポール・ボキューズ・・・1926年、リヨン近郊のコロンジュ・オ・モン・ドールの料理人の家系に生まれ、「ラ・ピラミッド」など多くのレストランで修業を積んだ後1959年に生家のレストラン「ポール・ボキューズ」を継ぎました。1961年にはフランス政府より国家最優秀職人章(MOF)を授与され、1965年に得たミシュランの三ツ星を40年以上にわたって維持し、「ヌーベルキュイジーヌ」の旗手として国際的な知名度とともに現代フランス料理界で特別な存在となっています。
フランスには6年ほどいましたが、日本へ帰ろうという気持ちはありませんでした。フランスからカナダへ行って、アメリカに入って、そこらで何かやろうという野心を持っていました。でも、家庭の事情があって日本に帰らなければならなくなって、帰国後にまた仕事探しが始まります。自分の考えとしては、東京のレストランで働いて将来的にはレストランをやりたいと思っていました。そうこうしている内に、ポール・ボキューズさんが大阪のホテルプラザに顧問として来ることを知って、今度こそ一緒に仕事がしたいと申し入れをしたのです。それでやっと願いが叶い、彼とは3年、そしてボキューズさんの兄弟分だったルイ・ウーティエさんと4年間仕事をしました。その頃、30代前半でしたが様々なホテルからオファーをいただくようになり、その中で私の意向を全面的に受け入れてくれた大阪全日空ホテルに行くことにしたのです。そこで洋食の料理長兼レストランのシェフを任されたとき、約束したのは「大阪でナンバーワンのお店にする」ということでした。
横田シェフが総料理長を務めた、大阪全日空ホテルのフランス料理レストラン「ローズルーム」は、当時話題の格付誌「グルマン」で連続三ツ星を獲得しています。

・ ウィンナーシュニッツェル…ウィーン風のカツレツ。
・ モリーユ茸…アミガサタケ。
・ ブランマンジェ…「白い食べ物」の意味を持つ冷菓。古くは肉を使うレシピが多くみられる。オーギュスト・エスコフィエの著書では、デザートとして記されている。

大阪全日空ホテルの総料理長を務めたあと、品川のストリングスホテルの立ち上げと東京の全日空ホテルの全面改装を任されました。コンセプトを作って道筋を作ってほしいということで、レストランやバーの洋食部門を手がけました。そうしましたら、無事に売上増を果たしたのですが、ANAからインターコンチネンタルホテルズグループに運営を任せることになり、2年間務めてホテルは退職しました。その後、全日空の本体との契約で、機内食の企画などのプロデュースの一端を担っています。
そんな中、ここ「ル・ヴァンサンク」が店を閉めるつもりだということを聞きました。オーナーから相談があって、最初は新しいオーナー探しのお手伝いをしたのですが、結局私がオーナーとして引き継ぐことにしたのです。それから、設備投資をして全面的にリニューアルをしました。当時創業33年の歴史あるお店を継承し発展させたいという思いがあってのことでした。また、若い頃に描いた料理人としての原点、レストランをやりたいという夢が人生の後半で叶うことになったのは、ホテルで料理人をやってきた私にとって運命であったのかも知れません。
最近では、今年の4月に倉敷でレストラン「ヴァンサンク」をオープンさせました。倉敷は大原美術館などに象徴されるように文化的にレベルが高いところだと思います。そんな場所にイギリスの町をイメージした建物を私の姉が建て、ル・ヴァンサンクが経営をしています。このお店はカフェレストランというスタイルで、フレンチでありながら気軽にお越しいただけるようにコーヒーや朝食などもあります。まだオープンして間もないのですが、フランス料理を気軽に召し上がって頂けるレストランとして沢山のお客様にお越しいただいています。

私はフランスへ行って、日本で暮らしていた時は感じなかった日本人としてのアイデンティティを初めて感じたように思います。異国の文化に触れ、個性を大切にする国民性の中で生活する内に、日本はアジアの極東にあったことで、吹き寄せの文化を形成してきた「無形の文化」なのではないかと思いました。それは決して悪い意味ではなく、精妙な技術を携えながら多様的で柔軟性を持った素晴らしい文化であると思ったのです。シルクロードを西から東へ様々なものが伝わり、中国や韓国から日本へたどり着いたとき、日本人は好奇心を持ってそれらを受け入れ、限られた材料や情報の中から巧みな技術によって、日本文化に合う精巧なものを作り上げてきました。
料理においても海外の良いものを取り入れ、そこに日本のアレンジを加えて新しいものを作り出してきました。例えば、コートレットはトンカツに、オムレットはオムレツに、キュリはカレーライスに、ハッシはハヤシライスに。これらは全部フランス料理が元になっているのです。これほどまでに他国の料理に対して情熱を持って勉強するのは、日本人だけではないでしょうか。ですから、フランスへ行って料理を学び吸収できたのも、私が日本人であったからだと思います。昨今、多くの日本人が海外へ進出し、その国の文化を吸収してまた新しい文化を生み続けているように、日本人というのは本当に好奇心が強く、良い目を持った器用な民族だと思います。

時代の流れと共に、料理も人の料理に対する価値観も変わって行きます。その中で我々が提案するクラシカル・モダンとは、歴史を重んじながら新たな時代の息吹を取り入れて生み出す料理なのです。
■店舗情報■
ル・ヴァンサンク|大阪市中央区西心斎橋1-9-31 辻本ビル1F (2014年3月閉店)
カフェレストラン ヴァンサンク|岡山県倉敷市羽島274-1|電話086-441-9702|定休日 火曜日
2009年に新たな歴史に向かってリニューアルされた「ル・ヴァンサンク」。 趣のある木のドアを開くと、クラシックで気品のある雰囲気と洗練されたサービスに迎えられます。 これまで培って来た技術を若いシェフたちに伝えながら、今もなお新しい料理を求め、好奇心と探究心を持って厨房に立ち続ける横田オーナーシェフ。そのお話からは、料理への愛情と情熱が本当に伝わってきました。お客様の中には著名人の方も多くいらっしゃるそうで、素晴らしいお料理に加え、楽しいお話やお人柄にファンになられる方が多いのではと感じました。 横田オーナーシェフの確かな価値観に、前衛的な要素が取り入れられたお料理の数々。「ル・ヴァンサンク」は、これからも訪れた人を幸せにするフランス料理のお店であり続けることと思います。
(2013年5月取材・文 島田優紀子)
*次回の「賢人の食と心」も是非ご期待ください。