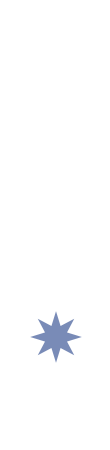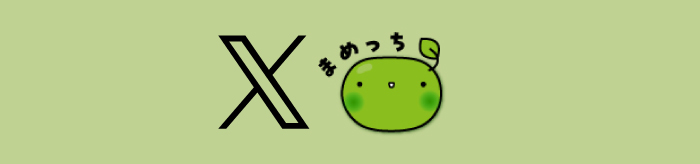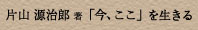川石本家酒類合資会社
料理の味が決まらないとき、ほんの少し加えるだけでまとまりをもたせてくれるみりん。キッチンの頼れる調味料ですが、ラベルの表示を見て「あれっ?」と思ったことはありませんか。同じもののように見えて「本みりん」「みりん風調味料」「発酵調味料」には明らかな違いがあります。昔ながらの製法で本みりんをつくる老舗で尋ねました。

川石本家酒類合資会社
兵庫県姫路市手柄148番地 079-223-0896
1863年(文久三年)の創業以来、代々受け継がれた技法でみりんづくりを続ける老舗。自社栽培の米を使い、安全で安心できる商品を届ける。原材料をもち米、米麹、米焼酎と国産米のみで製造したものや、10年もの歳月をかけ熟成させた本みりんなど、商品へのこだわりは尽きない。大手メーカーでは難しい細かな手仕事から生まれる味は、まろやかさとコクがあり、そのまま飲んでも味わい深いのが特長。和食料理人はもとより世界の料理関係者から評価されている。
みりんはみりんでも…

川石本家酒類合資会社で製造しているみりん。レギュラータイプや純米・槽しぼり、米だけのみりんなど種類豊富です。
魚の煮つけや野菜の煮もの、鶏の照り焼きなど、和食に欠かせないみりん。料理にテリやツヤを与えるだけでなく、上品な甘さとコクを深め、煮崩れも防止してくれる優れた調味料です。一口にみりんと言っても、スーパーの陳列棚にはいくつもの種類が並んでいます。購入する際にラベルを見て、「本みりん」「みりん風調味料」「発酵調味料」の違いがあることに気づき、どれを買ったらいいんだろうと迷った経験がある人もいるのではないでしょうか。
一見するとすべて同じもののようですが、中身は似て非なるもの。日本人が昔から活用してきた伝統の調味料が本みりんであり、みりん風調味料や発酵調味料と記されたものは本みりんの類似調味料です。みりん風調味料と発酵調味料は本みりんと比べると安価。出来上がる料理の味に差し障りがなければ安い方が家計も助かるし……と思いがちですが、それは安易な選択。種類によって製造方法や原材料が違い、味や料理に与える効果にも大きな差が生まれるのです。
3つの「みりん」の違い

製造場のすぐ裏手にある田んぼを含め計6反で自社栽培米を毎年育てています。管理をするのも川石さんの大事な仕事。
本みりんの原材料は米、米麹、焼酎または醸造アルコールなどです。熟成により麹菌が米の成分を分解し、糖類などが生成される糖化熟成という製法によってつられています。アルコール度数が14%ほどあるため酒類調味料に分類され、酒税がかかってきます。
発酵調味料の原材料は米、米麹、糖類、アルコール、食塩などです。販売時はみりんタイプ調味料や醸造調味料と表記されていることが多く、塩分が2%ほどあるため加塩みりんとも称されます。みりん風調味料とは異なりアルコール度数は8~20%ほどありますが、塩分を加えているため飲用とは見なされず、こちらも酒税がかかりません。アルコールが添加されている分、料理の風味を高める効果が期待できる一方で、調理の際は塩味を調整する必要があります。
みりんは女性好みの甘いお酒だった

こちらが製造場。普段は川石さんが一人で作業を行いますが、仕込みに忙しいときは5、6人の杜氏が手伝ってくれるそう。
みりんの発祥についてははっきりとはわかっていません。諸説ある中で有力とされているのは2説あり、1つは中国清明の時代に「蜜淋(みいりん)」と呼ばれる甘いお酒があり、それが日本へと渡り広まったという説。もう1つは、博多が発祥とされている練酒(粘度が高く甘酸っぱい酒)や甘い白酒に腐敗を防ぐ目的で焼酎が加えられたことがみりんづくりのきっかけになったのではないかという説です。
江戸時代の風俗を綴った『守貞漫稿』には、戦国時代の人々の間でみりんが飲まれていたという記述があります。甘く口当たりが良いことから、最初は調味料としてではなく、女性やお酒に強くない人でも楽しめる嗜好品として広がりました。そのころ江戸では、みりんを焼酎で割って甘さを抑えた本直しと呼ばれるアルコール飲料がブームにもなっていたほど人気だったとか。今でいうスイートワインのような感覚で親しまれていたのではと川石さんは言います。
「昔は正月のお屠蘇といえばみりんでした。でも今は調味料の印象が強いので、そのまま飲むなんて想像もできないという人が多いようです。イベントなどでお客さんに試飲を勧めることがありますが、最初は皆さん嫌厭されますよ。でも少し口をつけてもらうと、みりんってこんなにおいしいの?と驚かれます」。
飲料としてのおいしさを追求し製造技術を進歩させていった結果、甘味がアップ。江戸時代後期には砂糖の代わりとしてうなぎのたれやそばつゆに利用するようになりました。以降、調味料として料理店で用いる機会が多くなったものの高価で、一般に普及するようになったのは昭和30年代から。大幅な減税がなされたことで徐々に家庭でも使われるようになっていったのです。
丹精込めて育てた米が味の軸

熟成が進むタンクの中をよく見ると、ふちから黄色の液体が浮き上がってきているのがわかります。整然と並んでいるのは本みりんづくりに必要な道具。杜氏たちの力を借りながら、今年も新しい味が生まれます。
流通しているみりんの多くは原材料と製造の大半を海外に依存しているのが現状です。大手メーカーなどでは中国やベトナムなどに製造工場を持ち、現地の米でつくったもろみを輸入。搾りの作業を日本で行うことで原価を極力抑え、安価での販売を可能としています。
しかし川石さんは、先祖が大事にしてきた高い品質を守るため、海外に頼ることをよしとはしません。みりんづくりに使うもち米と麹米は自社が持つ田んぼと近隣の耕作放棄地を借り、毎年自ら栽培しています。生育に欠かせない水はそばを流れる川から引くのではなく、わざわざ自分で掘った井戸の水を与えるというこだわりよう。「米の味を確かめる食味計で測定すると、川の水で育てた米と井戸水で育てた米には5点ほど差が出ます。このわずかな違いがみりんの味に大きく影響してくるんですよ」。
自社栽培米を使うのは創業当時から貫いてきたやり方です。「昭和の大量生産の時代にはこんなに細々とやっていることに恥ずかしい気持ちもありました。でも今となっては米づくりから取り組める製造元はそうないし、小さな蔵だからこそできる強みでもあります。海外に頼るとコストダウンができることはわかっていますが、今は原材料の産地にまで消費者が意識を向ける時代。今のままの味でお客さんには喜んでもらっているので、手間はかかっても昔からのやり方は手放すことができません。ゼロから自分で手掛けているので、出来上がった商品への思いもひとしおです」。
先代譲りの製法を受け継ぐ

もろみを絞る槽(画像上)。麻袋に入れたもろみを並べて何層にも重ねて、上から圧力機で圧をかけていくとみりんが染み出てきます。搾って出てきたみりんはポンプでタンクに送られ再び寝かす工程へ。現在は20本ほどのタンクを管理しています。
昔は日本各地の酒蔵でつくられていた本みりん。現在は愛知県三河地方が本場とされていますが、兵庫県姫路市を中心とする播州地方もかつては三大産地の一つに名を連ねていました。温暖な気候と豊かな風土に恵まれ、原材料に欠かせない穀類がよく育ったことから、10軒以上の酒蔵が技を競い合って製造していた時代もあったといいます。けれども次第に数が減少し、今では地域でわずか一軒を残すのみとなりました。
150年以上もの長きにわたり、昔ながらの製法で本みりんをつくり続けているのが川石本家酒類合資会社です。製造場のある本社までは姫路城から車で15分ほど。空に向かって堂々とそびえるレンガ造りの赤い煙突が目印です。「建物は創業当時から大きく変わっていません。昔使っていた馬小屋もそのままです」と話すのは社長の川石酒志さん。先祖が代々守ってきた地で、伝統の技を受け継いでいます。
川石さんによると、昔の酒蔵では日本酒、みりん、焼酎をつくり、年間の製造スケジュールが決まっていたとか。「秋に米を収穫したらまずは日本酒をつくり始め、ひと段落する2月くらいからみりんづくりを行っていました。5月ごろまでにみりんを仕込み終えると、次は焼酎づくり。そうやってどの蔵も1年の仕事が回っていました」。すべての製造においてなくてはならなかったのが杜氏の力。さぞかし目まぐるしい毎日をおくっていたことでしょう。
伝統にならって仕込む本みりん

出来上がったみりんを瓶に詰めたりラベルを貼ったりする作業は夫婦二人三脚でこなします。
川石本家酒類合資会社での本みりんの仕込みは寒さが最も厳しい2月初旬に始まります。昔は全工程を手作業で行っていましたが、杜氏の高齢化や人件費削減のため、今は一部の作業を機械に任せることで効率化を図っています。
まずは米を洗米し蒸米機で蒸した後、麹菌をふりかけ米麹をつくります。次にもち米と米麹を焼酎と混合。ドロッとした液体(もろみ)になったところでタンクへと移します。タンクの中で60日から70日間寝かせると米麹の中にある酵素が活発化。もち米が持つデンプンやタンパク質を分解し、アミノ酸などのうま味成分やみりんらしい香りが育まれていきます。
もろみが眠るタンクの中を見せてもらいました。1ヵ月ほど熟成させた表面にはうっすらと黄色の液体が浮き上がっています。これは順調に糖化が進んでいる証拠だと川石さん。糖化熟成中はタンクの中が麹菌にとって最も活動しやすい30度前後に常時保たれているのが理想です。微妙な温度変化が品質を大きく左右するため、昼は練炭、夜はボイラーを使い、安定した環境に整えることが川石さんの役目。あとは自然の力にゆだねながら静かに見守ります。
無事糖化熟成を終えるともろみを麻袋に入れます。ここで登場するのが大きく深い浴槽のような槽(ふね)。その中に麻袋を積み重ね、圧搾機で搾りにかけると袋の目からじわりと液体が染み出てきます。この黄金色に輝くしずくこそが本みりんです。搾った後はすぐに出荷せず、再びタンクの中で寝かせることでさらに円熟味のある味に成長。手塩にかけた本みりんは1本ずつ手作業でラベルを貼付し、年間に一升瓶で約8000本が旅立っていきます。
【コラム】本みりんの副産物「こぼれ梅」って?
みりんを搾り終え、麻袋に残ったもろみは日本酒ならば酒粕のようなもの。白くほろほろとした見た目を満開の梅が咲き誇る様子に重ね合わせ、こぼれ梅という名前で呼ばれています。こぼれ梅は栄養価が高く、江戸時代の人々はお菓子として食してきました。最近は専門家たちによる研究が進み、美容と健康に効果的な食品として見直されてきています。 こぼれ梅はみりん特有の甘さやうま味を残し、調理に使うとふくよかな味わいが膨らむのが魅力。酒粕と同様のアレンジが楽しめ、味噌汁や甘酒、粕漬などに利用することができます。昔ながらの製造過程でしか生まれないこぼれ梅はいわば希少品。見つけたときはぜひ買い求め、珍しい味を堪能したいものです。熟成を重ねた味はプレミアム

国産米で焼酎をつくり、米だけで仕込んだ新商品。食にこだわる人に向けた川石さんの自信作(画像上)。川石さんが試作中の10年熟成本みりんを使ったプリン(画像下)。黒糖に近い味のカラメルソースが美味です。
愛情をかけた商品の中でも「10年熟成本みりん」にはひと味もふた味も違った魅力があると胸を張る川石さん。同社のみりんは高温処理を施していないため、瓶詰をしてからも麹菌が生き続けています。その特性を利用した10年熟成本みりんは、タンクの中で長年継ぎ足してつくられてきた逸品。味、香り、色が経年とともに深みを醸し出し、濃密な味わいと上品なまろみは料理に加えてなお存在感を放ちます。特に乳製品と相性が良く、有名ホテルのフレンチシェフもチーズとのマリアージュに太鼓判を押してくれたとか。
川石さんはみりんの新たな可能性を追い求め、10年熟成本みりんを主役にしたスイーツを試作中です。「いろいろと試みてプリンはどうかなと。10年熟成本みりんを半分の量になるまで煮詰め、カラメルソースの代わりにしてみたんです」。試作品をいただいてみると、みりんに黒糖のようなコクが生まれ、あっさりとした甘さ。和の香りもほんのりと漂い、大人のための甘味といったところです。
簡易な味に押され姿を潜めつつある本醸造のみりん。川石さんは今こそみりん本来の実力を知ってもらうときだと語ります。「一度本物の味を知ったらきっと手放せなくなるはず。まずは一人でも多くの人に口にしてもらうきっかけづくりをしないと」。ひたむきな努力は続きます。
【コラム】本みりんの多彩なアレンジ
本みりんのユニークな味わい方を川石さんに教えてもらいました。気になる人はぜひお試しを。
①本みりん×柑橘類
本みりんにレモンやゆずなどの柑橘類を好みの量だけキュッと搾るとさわやかなドリンクに。
②本みりん×コーヒーor紅茶
砂糖代わりに本みりんをスプーンで1~2杯程度をプラス。アルコール成分により体の芯からポカポカ。
③10年熟成本みりん×アイスクリーム
本みりんとバランスの良い乳脂肪分が低めなアイスクリームの上に回しかけると、ちょっとリッチなスイーツに変化。