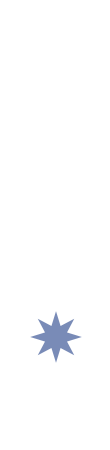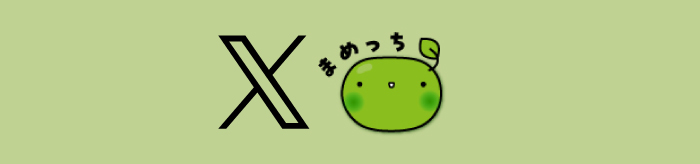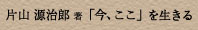梅乃宿酒造
大和の酒づくりに勤しむ「梅乃宿酒造」。伝統や文化の枠にとらわれず、時代の今をとらえて発信する味は、日本のみならず世界の人々の心も引き付けています。

梅乃宿酒造
奈良県葛城市東室27
0745-69-2121
https://www.umenoyado.com
奈良県葛城山の麓に蔵を構える明治26年創業の酒造会社。良い原料と高精白にこだわり、葛城山系の伏流水を仕込水に大和の地酒を作り続ける。オートメーション化が進む業界で、人の手により生み出される酒づくりに注力。2001年からは日本酒蔵でありながら日本酒に梅を漬け込んだ梅酒の製造・販売を開始する。近年はたっぷりの果汁や果肉をブレンドした日本酒ベースのリキュール「あらごしシリーズ」が大ヒット。国内のみならず世界でも愛されている。
チャレンジをモットーに

蔵の庭にある樹齢300年を超す梅の木。梅乃宿という名前は、毎年春になるとこの梅の木にうぐいすが飛来することにちなんで(画像上)。
男性社会の日本酒業界で、吉田さんは貴重な存在。繊細な感性と持ち前のバイタリティーで、業界に新風を巻き起こす商品を生み出しています(画像下)。
日本清酒発祥の地とされる奈良県に蔵を構えて126年。創業200年、300年の歴史を持つ蔵が珍しくない業界で、梅乃宿酒造は比較的若い会社です。
「うちなんてまだまだ新参者ですよ」とにこやかに話し始めた社長もまた若き女性。吉田佳代さんは先代の父親から2013年に会社を受け継ぎ、5代目に就任しました。伝統や格式を何よりも重んじる日本酒の世界において、梅乃宿は少々型破り。日本酒のもつ可能性を広げていきたいと、昔から新しいことにチャレンジするのをモットーとしてきました。その一歩は、3代目が取り組んだ自社ブランドの吟醸酒製造に始まります。
「かつて日本酒は特級、1級、2級と級別に分類されていて、当社では毎日愛飲できる晩酌酒を大手メーカーから依頼を受けて製造していました。流れが変わったのは昭和30年から40年ごろ。3代目が自社ブランドの生産に比重を置くようになり、まだ吟醸酒という名前もなかった時代から良い酒を作ることに力を注いできました」。
理解されなかった自社精米

梅乃宿の最上級銘柄。山田錦を35%まで磨き上げ、匠の技を傾注させた純米大吟醸です。2016年まで7年連続モンドセレクション最高金賞を受賞。
時代の先を読み良い酒づくりを行っていくという考え方は、4代目にも引き継がれました。4代目が着手した新しいチャレンジは、自社精米による酒づくりです。当時、原材料となる米は委託精米を行うのが一般的でした。梅乃宿が始めた自社精米はリスクが大きく、なぜわざわざ自社でする必要があるのかと首をかしげる同業者が多かったといいます。
「設備を導入するだけでも数千万。定期的にメンテナンスも必要で、人もつけないといけない。委託しておけば経費も抑えられて楽なのに、一体何をやっているのだと理解されませんでした。けれども、より質に磨きをかけて良い酒を作るには取り組むべきことだというのが4代目の考えでした」。
今では自社精米が特別なことではなくなり、米の栽培から一環して行う蔵も増えました。梅乃宿はこのようにいつの時代も業界の常識を覆し、独自の方法で新たな道を切り開いてきたのです。
蔵人の年間雇用を実現

香り高い国産の梅を使った梅乃宿の梅酒。丹精込めて丁寧に手仕込みした味は、上品な梅の香りとコク、まろやかさが伝わる至極の逸品。
平成に入ると、梅乃宿はさらに業界を驚かす取り組みを開始します。なんと、蔵人の年間雇用制度を採用したのです。蔵人は杜氏の指揮のもとで酒づくりに携わる技術者。昔は農閑期や漁閑期の出稼ぎとして定着していました。ところが、年々農家や漁師は減り、人手不足が深刻化。現役の蔵人は高齢化する一方で、若い担い手も期待できなくなっています。従来の蔵人の働き方が、今にマッチしていないと感じた4代目は、大胆に雇用方法を切り替えることにしました。
「技術を継承していくためには、地元で若い人を採用し自社で育てていくしかないと。けれども、日本酒は冬にしか仕込まないので、夏は蔵人の仕事がありません。だからといって夏は自由にしてもらっていいといえば、やはり人材の確保は難しくなります。年間雇用を実現するためには、1年を通してコンスタントに蔵人に仕事がないといけないわけです。だったら、夏は梅酒をつくればいいという先代の発案から、自社で梅酒づくりを行うことになりました」。
梅の実が実るのは5月から7月にかけて。ちょうど日本酒づくりの手が休まるころに梅酒は製造の最盛期を迎えます。こうして売り出すこととなった梅酒が、梅乃宿を急成長させることになるのです。
梅酒ブーム到来で大躍進

これまでの歴史の中で、変えていないことの一つは日本酒を作り続けること。日本酒がリキュールの利益を下回っても、日本酒の酒蔵という誇りは忘れません。(画像上)。伝統を大切にしながらも時代を読み、製造方法を変化させてきた梅乃宿。技を次世代へ伝えるために、時には大胆な改革も必要だといいます(画像下)。
「初年度はタンク1本分の梅酒を製造しました。するとあっという間に売り切れ、2年目はタンク2本に増量。またまたすぐに完売し、3年目は思い切ってタンク20本分を仕込むと先代が言い出して。さすがに社員も驚いて、やりすぎなんじゃないかとざわつきました(笑)。でももう梅の実は発注済み。大量に届くので漬けなければ仕方がないですよね。みんなで一生懸命梅酒を仕込んだら、翌年になんと梅酒ブームが来て。他の蔵でも日本酒で梅酒を漬けているところはありましたが、どこも少量なのでニーズに応えきれずに品切れ状態が続いていました。ところがうちはしっかりと在庫があり、味もおいしく、価格も安いということで注文が殺到。結果、全国に商品が広がり、名前が知られるようになりました」。
業界では日本酒蔵が梅酒をつくることはタブー。梅乃宿が製造を始めた当初は、大バッシングを受けました。
「業界の恥さらしとか、もう梅乃宿は潰れるとか、梅酒ばかり作っていないでいい日本酒も作れとか。いろいろと厳しい声もありました」と、吉田さんは苦しかった日々を振り返ります。ブームのおかげで、わずか数年で梅酒市場は確立。梅乃宿に批判を浴びせていた他の蔵も、手のひらを返して梅酒製造を行うようになり、状況は一変しました。この件から、長く培ってきた文化や歴史も一瞬で大きく変わることがあることを身をもって知ったという吉田さん。自社が長年掲げてきた酒づくりのテーマ「伝統と革新」がもつ言葉の真意を深く心に刻みます。
「伝統だけに偏ってしまっては上手に道を走ってはいけません。伝統と革新の両輪がバランス良くあってこそ初めてまっすぐ進むのではないかと思うんです。そして革新が次の伝統をつくるとも思っています」。
「あらごし梅酒」誕生秘話

「あらごし梅酒」が火付け役となり、食感のある酒が一躍ブームに。日本酒の可能性を広げました。
梅酒の大ヒットに端を発し、またしても梅乃宿から業界の既成概念をくつがえす商品が誕生しました。それが「あらごし梅酒」です。すりつぶした奈良県西吉野産の梅の果肉を梅酒にたっぷりとブレンド。華やかな香りが広がり、濃厚でとろりとした口当たりは独特で、まるで梅の実そのものを食べているような逸品です。他社のものとは一線を画す新鮮な味わいが消費者にうけ、あっという間に梅乃宿を代表する看板商品へと登り詰めました。実はこの「あらごし梅酒」、ある問題を解決するため、社員みんなで知恵を絞り生まれたもの。
「当社の梅酒が大人気になったのは良かったのですが、今度は漬けた梅の実が大量にあまるようになってしまって。食品業界に身を置くものとして、廃棄するのは胸が痛みます。もったいないとジャムに加工したりもしましたが、思うように売れない。どうにか活用する方法はないかとあれこれ模索するなかで、種を取ってすりつぶし、梅酒に入れて飲めるようにしてはどうかという案が出たんです。確かに、瓶の中に梅の実がゴロゴロと入った商品はありましたが、取り出して食べないといけない手間がありました。お酒と混ぜてしまえば、タンクにも瓶の中にも実が残らず、そのまま飲んでもらえて一石二鳥というわけです。お酒でありながらザラザラとした食感が楽しめるものはなかったので、強いインパクトを残し、思いがけずお客様に喜んでいただける商品となりました」。
果汁量の多さと安定供給が強み

「あらごしシリーズ」は国産の果実を厳選。香料など人工的なものに頼らないナチュラルな風味を1本に凝縮させています。
果実感とナチュラルな風味が魅力のリキュール「あらごしシリーズ」は、梅乃宿の新たな主力商品として不動の地位を確立。もも、ゆず、みかんなど、どんどんと種類を増やしヒットを連発しました。日本酒とは縁遠かった若い女性層にファンの裾野を広げ、今では売り上げの8割を占めるまでに成長しています。自社の商品が他社のものより支持されている理由を、吉田さんは次のように読み解きます。
「一つは果汁量の多さ。当社は原材料となる果実の質にとことんこだわります。産地にも足を運んで、栽培環境や栽培方法を確認し、果実のしぼり方にまで目を光らせています。もう一つ、気を配っているのは品切れさせないことです。日本酒業界は希少価値を高める売り方をするところが多いのですが、あらごしシリーズはあえて真逆を選択。定番商品として常に在庫を持ち、いつでも提供できる安定感を打ち出しました。そのほうが飲食店ではメニューを入れ替えずに済み重宝されます。品切れさせないために、私たちはまず質の良い原材料の確保に力を注ぎます。あらごしシリーズは国産の上質な果実が味の生命線。たとえばゆずなら、全国各地から果実を仕入れていますが、酸が強い、香りが高いなど、産地ごとの特徴を捉えることが品質管理の基本。そのうえで毎年ブレンド比率を変え、同じクオリティの商品を生み出す努力をしています」。
若手社員たちが力を発揮

「FRUTAS(フルータス)」はブラッドオレンジやマンゴーといった海外のおいしい果実をアレンジ。常に新しさを追求しています(画像上)。
酒づくりに携わるのは若いメンバーたち。フレッシュな感性が革新的な商品の誕生に結びついています(画像下)。
こうした梅乃宿の快進撃を支えているのは、平均年齢約37歳という若い社員やスタッフたち。いつも広くアンテナを張り、枠にとらわれることなく商品開発に取り組んでいます。年齢や経験、立場に関係なく自由に発言できる風通しの良い職場環境が、時代にフィットする名品を生み出す原動力。消費者のターゲットを20~30代女性に設定しているリキュールは、味・ラベル・価格の決定権を女性社員・スタッフが握り、市場のリアルな声を商品に落とし込んでいます。2017年からは若い感性をさらに生かす大胆な取り組みもスタートしました。
「実は杜氏制度を廃止しました。日本酒づくりを司る杜氏は仕込みの現場では絶対的な権力を持っています。良くも悪くも杜氏の意向が強く反映された酒になってしまうことが、私の中でひっかかっていました。杜氏1人の肩にのしかかる負担や責任も分担できるように、当社では現在3人トップ体制を取っています。各々に一応は役割分担があり、1人は現場を見る製造課長、もう1人は内外の交渉ごとなどを担当する製造部長、残る1人はデータ分析などを行う企画開発課長。それぞれの得意分野を生かす形で配属しています。1人では足りない部分は3人で補い合い、調和を取りながら酒づくりをリードしてくれています。味にもいい意味で変化が現れるようになりました」。
海外にも広がる梅乃宿ファン

海外でも支持されている「梅乃宿ゆず」。天然ゆずの香りが爽やかに立ち、酸味とほんのりとした甘味が感じられます(画像上)。
近年は海外の展示会にも積極的に出店。現在は全体の売り上げの2割を輸出が占めるまでになりました(画像下)。
梅乃宿は2002年から海外にも進出。台湾、アメリカ、中国など、22カ国に輸出しています。特に台湾では、ゆずといえば梅乃宿のゆずのリキュールを指すほど知名度を上げ、出荷量も増加。2017年にはアメリカに新会社を設立し、現地の嗜好に合わせた味やパッケージの提案を進めています。和食が世界的に流行していることは日本酒にとっても追い風。良い風に私たちも乗っていきたいと吉田さんは意気込みます。
「海外でのチャレンジは発見と気づきの連続。時には自分たちの当たり前が根幹から揺るがされることもあります。海外店舗の『一風堂』にゆずのリキュールを置いてもらっているのですが、日本人なら豚骨ラーメンと合わせるという発想は浮かばないと思うんです。どちらも味の個性が強すぎるので。でも海外の人にとってラーメンは和食。和食を食べるときは日本の酒が飲みたくなるわけで、日本の酒は日本酒もゆずのリキュールも同じという感覚なんです。実際に合わせてみると意外と相性が良くて、口の中もさっぱりするんですよ。こんな場面に遭遇すると、こうでなくてはいけないという勝手な概念に私たちはまだとらわれているんだと認識します。確かに伝統は大事。でも伝統を残していくためには変化も必要です。友禅染のアロハシャツやスーパー歌舞伎があるように、伝統に興味を持ってもらうための入口は柔軟にしておくべきなのではと考えます」。
まだ見ぬ新しい形を目指して

「梅乃宿の一番の誇りは人材。リキュールや日本酒がおいしいと思われることより、社員やスタッフがいいねと言われることのほうがうれしい」と吉田さん。
120周年の節目と吉田さんの社長就任が重なった6年前、梅乃宿は「新しい酒文化を創造する蔵」という新たなコンセプトを掲げました。技を守り研鑽していく一方で、伝統を軸に時代に合わせて価値のある商品も生み出していかなければ、この先日本酒は廃れていくばかりだと吉田さんは語気を強めます。
最後に、梅乃宿の今後の夢について聞きました。「120年以上、常に新しいことにチャレンジし続けることと日本酒をつくり続けるという基本はぶらさずにやってきました。今後もこの2つは大事にしながら、日本酒業界で新しい価値観を作っていくパイオニアでありたいと思っています。今はまだない新しいポジションや形を目指していきたいというのが本音。そして、社員やスタッフにとって働きやすい環境を保ち、みんなが誇りに思える会社にしたいですね」。
目の前にすでに見えている次のチャレンジは4年後。手つかずの自然が残る葛城山の麓に蔵と本社の移転を予定しています。新天地では社員やスタッフとお客さんが近い距離で接し、梅乃宿の魅力をより多くの人に伝えていくことに注力したいと目を輝かせる吉田さん。若い力を束ね、快進撃は続いていきます。