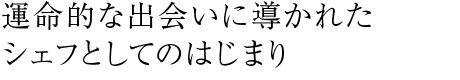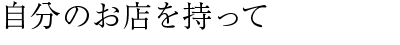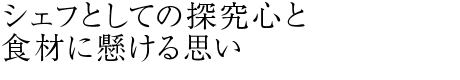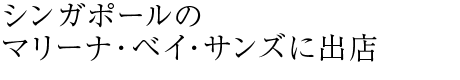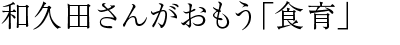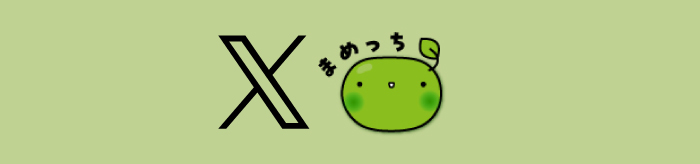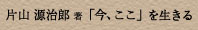赤い大地に渡った世界が認める日本人シェフ
今や世界のトップシェフに名を連ねる和久田哲也さん。真っ直ぐな食への情熱と飽くなき探究心をもって今日の偉業を成し遂げられ、数々の勲章や賛美の声を受けながら「僕は本当に運が良い。」と、ご本人はその人生をただ純粋に楽しんでいるようでした。
「僕は、シェフになろうと思ってなったわけじゃないんです。」 和久田さんが、ある夢を胸にスーツケース1つでオーストラリアへ渡ったのは30年前。多くの出会いに導かれ、思い描いていた夢とは違う道を歩み出します。料理もほとんどしたことがなかった22歳の青年が、世界に知られるシェフとなるまでにどんな道を辿って来たのでしょうか。

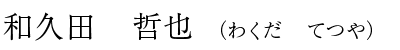
1959年 静岡県浜松市生まれ
22歳で単身オーストラリアへ渡り、29歳にして、自らがオーナーシェフを務めるレストラン「Tetsuya’s」をオープン。世界的なレストランガイドの上位に常にランクインし、オーストラリアNo.1シェフの称号を二度獲得。現在では、様々な活動を通じて、地域の経済活性化にも貢献されています。
2010年、シンガポールの総合リゾートホテル「マリーナ・ベイ・サンズ」にレストラン「WAKU-GHIN」をオープン。

僕は日本の大学を卒業してからすぐにオーストラリアに渡ったんですが、それ以前のことをインタビューなどであまり言わない一つの理由としては、別に隠しているわけじゃなくて、ちょっと変わった夢を持っていましてね。実は、子どもの頃からガンスミス、つまり銃の製作やデザインするような仕事をしたかったんです。だから、いつかアメリカに行って銃についての勉強しようと思っていました。でも、そんな夢があったなんてインタビューではなかなか言えないし、意外と今まで聞かれませんでしたしね。親父にはガンスミスになりたいという夢を小さい頃から言っていたので、この子は真っ当な人間にならないだろうと本当に思っていたようです(笑)。それで、大学に入ったのも実は口実で、家から離れて内緒で射撃の勉強をしていました。もちろん親には言えなかったですね・・・。海外へ行きたいと思ってはいましたけど、親にはお金は出してもらえませんでした。行ったら帰って来ないと親もわかっていたので絶対ダメだと。それでも海外に行きたかったから家を出て、大学に通いながら一生懸命アルバイトをしてお金を貯めました。そして、1982年の5月1日に日本を出てシンガポール経由でオーストラリアに行ったんです。
海外へ行ったのは、只々子どもの頃からの夢を叶えたいという思いでした。そして、そこから自分の人生が始まったような気がします。昔、ジャーナリストの兼高かおるさんの番組で「世界の旅」というのがあって、小さい頃に私はそれを親が不思議がるくらいじーっと見ていました。その頃から海外に憧れていたんだと思います。 僕が大学生の時代は、オーストラリアの1年間のビザを取るというと100万円必要だったんです。30年前の100万円は僕にとっては本当に大金でした。でも親には頼れないし。だから必死でアルバイトをして。そして、貯まったと同時にすぐに日本を出ました。でも何も明確な目的がないまま海外に出て、言葉も出来ないし、ツテも何もない。そんな状況でも、僕はとりあえず行けばなんとかなると思っていましたね。オーストラリアを選んだのは行ってみたい国の一つだったからです。もう一つはアメリカ。でも、今思えば非常に考えが甘かったですね、言葉なんかすぐに覚えられるだろうと。当初は、1年くらいオーストラリアにいて、その後はすぐにアメリカへ行こうと思っていました。
オーストラリアに渡り、まず住むところを借りました。そこはギリシャ人が貸していた家で、家賃を払いに行った時に、英語が勉強できる学校を紹介してほしいと家主に言いました。すると、その家主がすぐに車に乗れと。それで連れて行かれたのが「フィッシュワイヴス」というレストランだったんです。「レストランなら食事も出るし、言葉も学べてお金だって貰える。」って。今でもその家主のギリシャ人とは大親友なんですよ。そこから僕の皿洗い人生が始まって、レストランで働くようになりました。それから、3ヶ月くらい経った頃かな、スタッフに風邪が流行って何人も休んでしまったんです。毎日120人くらいお客さんが来るようなレストランだったので物凄く忙しくて、魚が来てもシェフ達は捌く時間がない。それで、シェフに捌き方を教えてやるからやれと言われて魚を捌かなきゃいけなくなりました。教えてもらいながら大きなトレイに積まれた魚をひたすら捌きました。初めての経験だったけれど、その日の午後にはそれなりに出来るようになっていました(笑)。どこかに日本人の器用さがあったのかも知れませんね。
そのとき「うまいな。」と言われて、それから魚の良い悪いとか種類を教えてもらうようになりました。最初はもう必死で書いて覚えましたね。オーストラリア英語っていうのは凄く癖があるんです。口を開けないんですよ。初めはそれでとても苦労しました。でも、半年ぐらいで大体言っていることはわかるようになりましたね。まだその段階ではまさかこれで生きていくなんて思っていませんでした。1年くらいしたらアメリカに行こうと思いつつ生活をしていたんです。そこのシェフとは今でも大親友なんですが、デニー・ホワイトと言って、本当に可愛がってもらったんですよ。言葉も出来なくて料理のことも何もわからないのに、普通に同じオーストラリアの人たちの条件で雇ってくれて。彼は「我々が美味しいものを食べなかったら、どうやって美味しいものを作るんだ?」という考え方でした。シェフ達とも仲良くなって休みの日はごはんに連れて行ってもらって、だんだん料理を覚えていきました。
そうこうしている内に、フィッシュワイヴスにいたマネージャーが「キンセラーズ」というレストランに行くことになったんです。しばらくして、その元マネージャーからトニー・ビルソン※1というシェフを紹介されました。その人は当時から非常に有名なフレンチのシェフだったんですが、「君は日本人か。うちで仕事しないか?」と言われたんです。それをデニー・ホワイトに相談したら、「お前、あそこで仕事ができるんだったらただ働きでもいいから行った方がいいぞ!」って言ってくれました。それで行くことになったんです。
※1 トニー・ビルソン・・・「オーストラリア料理界の父」として知られる世界有数のトップ・シェフ。モダン・オーストラリア料理というジャンルを築くとともに、オーストラリアの食文化の発展に多大な貢献を続けている。
その頃の僕は、本当に何も考えていませんでした。誰かにあそこに行けと言われれば行き、またどこかに行けと言われれば行って、そうしている内に料理を覚えることができたんです。それと、その2つのレストランの料理が本当に美味しかったこと。それがやっぱり運が良かったんだと思います。他のところで店を一から立ち上げる経験もさせてもらいましたし、また別の店ではそれまでシェフだった人が辞めるからといって急にメインでやることになったり・・・最初の皿洗いから4年が経った頃でした。

最初の店は27歳の時に5000ドルで買いました。キッチンなんてストーブ1個とオーブンとシンク、それだけでした。だから5000ドルだったんですけど。最初は店を改装するお金もなかったので、とりあえずという感じで始めて。1年半くらいは大変でしたね。色んな雑誌や新聞にお店のことを書いて頂いたんですが、いつもその後は数人が見ましたと来てくださるくらいで。だから、1年半経った頃、「ダメだなぁ。」とやめようと思っていたんです。今週いっぱいでやめようと心に決めていたんですね。それで、その週ですよ。前の週に来たというお客様から連絡があって。予約のお名前や時間などを聞いていると、自分はサンデーヘラルドのライターだと言われました。日曜日の新聞でコラムを持っているからということで来てくれることになって。でも、期待はしていなかったんです、全く。そのライターの記事にしていただいた日曜日のことです。当時、住むところがもうなかったのでお店の上で寝泊りしていたんですが、一日中店の電話が鳴り止まないんですよ。それから一気に連日満席になりました。それが、人生が変わった瞬間だったのかも知れません。でもさすがにキッチンが手狭でこれ以上は出来ないと思い、次は建物ごとお店を買いました。それが29歳の時。でも、その段階でもまだアメリカに行きたいと思っていましたね(笑)。
建物を丸ごと買って一番初めにしたことはキッチンのリフォームでした。一番初めの店の苦い思い出があるから・・・他のお店に行ってキッチンを見るとピカピカのステンレスで、何でうちのキッチンはこんなに貧しいんだろうと思うわけですよ。だから、買ってすぐにとんでもないお金をかけて直しました。お客様は前のお店から引き続き来ていただけたので最初から繁盛していましたね。それで、始めて2年くらいしてちょっとお金をためて、一回お店を3ヶ月ほど閉めてビルを完全に建て直してそのあと8年くらいそこでやりました。
それで今のお店、サントリーさんが所有していた建物を1999年の終わりくらいに話をいただいて、買い取ることにしました。土地は1000坪、建坪が4600平米くらいと大きいんです。どういうわけか向こうから話を持ってきていただき、「本社の意向で撤退が決まりまして、それでここを哲也さんにやってもらいたいんです。」と。当時からその建物は有名で、今でも大使館と言われているんです。ゲートはいつも閉まっていて、車で入って行かなければいけないんです。でも、さすがにその時は頭金すら持ってなかったので、頭金まで銀行に借りました。
数億とかのお金で買えるようなものではなかったので・・・買いますとは言ったけど。それに、自分が買い取ったときには庭が全部ダメだったのですべてやり直すことにして。最初はあんなにお金がかかるとは思わなかったんです。買うのはなんとか買えたんですが、色んなところを直さなきゃいけなかったから、途方も無いお金が掛かって来て、銀行のマネージャーにこれ以上出せないと言われたときに、「直せなくて店が開けられなかったら、今までのお金が全部パーだよ?」って話をしたら「あなたは悪い人だなぁ。」と言われました(笑)。それで、結局お金は出してもらえて、銀行から言われたノルマもクリア出来たんです。でも、やっぱり最初の頃は色々言われていたみたいです。「さすがのテツヤもあそこを買って終わりだな。サントリーでも出来ないところをテツヤがやってもダメだろう。」って。そんな時、僕のお茶の先生がいるんですが、「先生、ちょっと見栄張っちゃいましたよ。」って話をしたら、「あら、いいじゃないの。見栄を張れないような男はダメよ。見栄を張って背伸びして、背伸びしたらそこまで頑張ろうと思うでしょ。そこからまた背伸びすればいいのよ。そうじゃないと成長がないじゃないの。」と言われましたね(笑)。でも・・・正直言いますよ、僕は本当に運が良いと思います。凄く運が良い人間だと思います。
僕はシェフになろうと思ったことはなかったし、本当に料理人になりたくて料理をやっていたというよりも、やっている内に面白くて、気が付いたら料理人になっていたという感じですね。周りの人たちがおだてたり喜んでくれたりしたから、料理人になったという気がしないでもないです。ただ、この仕事は好きです。料理を始めて30年、自分の店を持つようになって25年なんですが、みなさんがよくおっしゃるのは、「苦労したでしょ?」とお聞きになるんです。でも・・・してないんですよ(笑)楽しかったという気持ちが多いんです。確かに大変ではあったけれど、周りの人の方が大変だと思ったかも知れない。でも、無ければ無いでそれなりに食べて行けたら良いし、我々のビジネスっていうのは暇だったら食材はあるから自分で作って食べられるじゃないですか(笑)。だから食べるには困らなかったですね。

料理に関して言えば、世界中の有名なシェフを知っていますし、色んな料理を食べて自分の中に蓄積して来ましたが、その中でもうちの料理はベーシックでとてもシンプルなんです。そこは変えないんです。料理の基本的な作り方はある程度本を見ればわかるけれど、自分のテイストをどれだけ入れるかですね。火の入れ方だって色々ありますから。その食材を見て見極めるんです。オーストラリアの場合って食材が本当に少なくて、食文化というものが元々ない国だから、本当に生産するところからしなくちゃいけないんです。自分がサーモンを紹介されたときに、それはそれで美味しいと思ったけれど、実はサーモンが獲れない時に出されたトラウト(マス)はもっと美味しいと思った。でも、臨時的なものだったんです。だから、サーモンが年間通して生産できるようになったらトラウトは生産しなくなる。
僕は魚としてはトラウトの方が絶対に良いと思ったので、トラウトを扱っている会社の中から僕が一番気に入ったところに行って、僕がほしいトラウトを作ってくれませんかと言ったんです。そしたら、バカヤロウと言われましたね(笑)。と言うのは、彼らは元々漁師がお金を出し合って会社を作ったんですね。だから、自分たちは漁師であって養殖の専門業者じゃないと。でも、僕はそれでも自分の希望を伝えたんです。こんなトラウトがほしいと。そして、トラウトの養殖を一緒にはじめたんです。
トラウトの養殖には「ペン」と言って、海の中に直径50~100mくらいのプールを作ってその中で育てるんです。オーストラリアの南にある島タスマニア州のマクオリハーバーと呼ばれているところの水は汽水域で、つまり上の2・3mは淡水で、その下は海水なんですね。普通の養殖トラウトは、海の水で育てるとどんなに上手くやってもエラの部分に病気が出来てしまうので、3ヶ月に1回は全部魚を上げて淡水に入れるんです。でも、そこの海は自然に淡水と海水の層があるので餌を食べるときには淡水のところに上がって来て、また海水へ降りて行く。だから、魚を水から上げなくていいから負担がなくて質の良い魚になるんです。ストレスがかからないから魚に抗生物質やホルモンを与えなくて良いし、自然の状態に近いから絶対に美味しい。うちが関係しているからではなくて、そうやって養殖した魚は絶対おいしいという確信がありました。
養殖以外にも天然の魚ももちろん使いますが、オーストラリア近海で獲れる魚というのはどれも油が少ないんです。それは水温が高いから、脂肪があまり必要ないんですね。油がちょっと欲しいなと思ったら油を咬ませれば良いんです。それで料理に使うんです。ハマチも身が締まっていて美味しいんですよ。簡単に食べるときは、そんな厚く切らないでお皿に乗せて、それで醤油と煮きったみりんとお酒を辛みだけ外して、ほんの少しのニンニクを隠し味で入れて、そこにオレンジの皮を細かく切って混ぜるんですよ。オレンジの皮は苦味が強くないほうがいいですね。それで、その上からコショウとオリーブオイル。オリーブオイルで油を出すとおいしいです。ほんと、うちの料理はそんな感じなんです。素材をどう活かすかっていう、それだけだと僕は思うんですよ。元々僕は日本で料理の勉強をしていたわけではないので、これでなきゃいけないっていうのがないから、それが逆に良かったのかなと思いますね。

僕がシンガポールに「WAKU GHIN」というお店を作ったのは、昔からやりたいと思っていたことがあって、お客さんがこういう料理を食べたいというと、それに応えられるようなゆったりしたお店を作りたかったんです。「WAKU GHIN」は4つに部屋が分かれていて、お客さんの目の前で料理ができるように特殊な温度調整が出来る鉄板を作らせて置きました。お客さんのリアクションを見ながらできるという、そんな造りにしたんです。広さは1000㎡あるんですが、席は25席。スペースの贅沢というか・・・無駄という贅沢だと僕は思うんです。だから、お客様に料理だけではなく、ゆったりした空間も味わっていただきたいと思っています。 それから、「WAKU GHIN」のグラスには昔から好きだったバカラ※2を使いました。オーストラリアは器がもう一つなんです。規制があって、鉛が入っちゃいけないとか物凄く厳しいんです。良い器を使おうと思えば使えるけれど、120人分のコースを揃えようと思っても手に入らないわけです。座席数が120席だと、料理の数は2000皿くらい作るわけですよ。中華でシェアできるような料理と違って、全員の分を一皿一皿作りますから。だから、シンガポールの店の話があった時に、僕は最初やらないと言ったんです。でも、好きなようにしていいと言われたので25という座席数にしました。
※2 バカラ・・・フランスを代表するクリスタルガラスのブランド。30%の酸化鉛を含むクリスタルガラスは透明度が高く、軟らかい。持ったときの重量感とグラスを合わせたときの高い金属音はバカラならではと言われている。
僕のレストランに行けばコーナーにオリジナル商品があるんですが、それはうちで使っているものを商品にしていて、うちで一番有名になったのは牡蠣(カキ)のソースなんです。牡蠣にかけるドレッシングがあって、それをお客さんにプレゼントしていたんですね。でもその内それが出来ないくらいにオーダーが入ってしまって。そんなある日、デビット・ジョーンズ※3の方が来て「うちで売りたい」と言われたんです。その時に軽く「良いですよ」と言って牡蠣のソースを差し上げたのがきっかけで、商品を作るようになったんです。そうしたら「もっと商品がほしい」と言われて、うちで使っているものをそのまま作ってもらうようにしたんです。トリュフの塩という商品があるんですが、うちのは絶対に香りが飛ばないんです。そういう研究なんかもしたりしていますね。
※3 デビット・ジョーンズ・・・シドニーを中心に展開する世界の一流ブランドが並ぶ高級老舗デパート。
食育という言葉にすると何か難しいような気がしますが、やはり今の自分があるのも・・・我々の時代の母親っていうのは料理が上手だなと思うんですよね。お味噌汁ひとつにしてもちゃんと出汁を取っていたし。母は三重の生まれでしたので、お味噌はその地元のものを使っていましたね。食べることが好きな家族だったので、週末はあそこのお寿司が美味しいから食べに行こうとか。そういう子どもの頃に美味しいものを食べていなかったら、今のシェフとしての僕は存在しなかったと思います。味覚は子どもの頃に形成されると言われていますからね。「お腹が空いたからと言って何でもいいから食べる」そういう時代はもう終わったと思うんです。オーストラリアで「マスター・シェフ (料理人バトル)」という料理番組があるんですが、その中でジュニア・マスターという10歳や11歳の子が料理をして、僕もジャッジをしましたが半端じゃなく上手なんです。それでその子の親に話を聞いていたら、料理が大好きでとても仲が良いんです。子どもがとても小さい時から一緒にキッチンに立って、一緒に作っていたから自然に出来るようになったんですよって。でも、それって究極の食育じゃないですか。 美味しいものって例えば高級なフレンチを食べなきゃいけないっていうことではなくて、素材自体が良いものを食べるということだと思います。 僕は食べる情熱があって作る情熱が生まれると思うんです。もっと美味しいものを食べたいという情熱が良い食材探しにも繋がりますし。だから、僕はお店で美味しいものに出会うと「これどこで手に入るの?」って聞くんですよ。恥ずかしいと思ったことは一度もありません(笑)。
その柔らかな口調と穏やかな笑顔の裏に秘められた情熱と行動力こそが、数々のチャンスを導き、そして多くの人に愛される料理を生み出して来たのだと、これまでのお話しを伺いながら強く感じました。世界中の料理サミットに招かれ、オーストラリア政府から勲章まで授与された和久田さんですが、全く気取るところがなく、とても紳士で温かい人柄ということがその言葉や仕草から伝わって来ました。最後に、「お逢い出来て良かった。」と握手をしながらひとこと。和久田さんはそうやって人との出会いを心から大切にされてきたのだろうと思いました。オーストラリアに渡ってから30年。今日も料理と真摯に向き合う和久田さん。「おいしいものを食べたい。」、そして「ベーシックな部分は変えない。」、その2つのシンプルな想いと理念がオーストラリアのみならず世界に認められたシェフ「TETSUYA WAKUDA」の原点であり、哲学なのかも知れません。
(取材・文 島田優紀子)
*次回の「賢人の食と心」も是非ご期待ください。