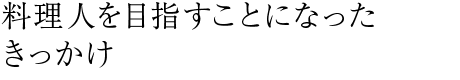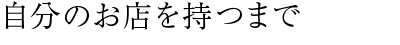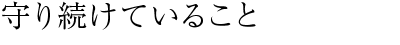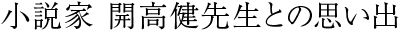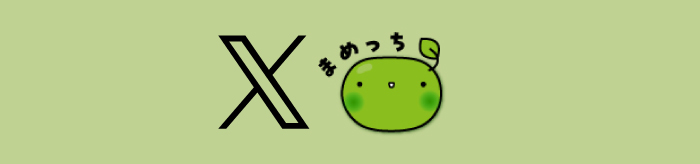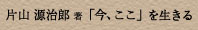江戸前は手から手へ 心を伝える鮨職人の仕事
日本屈指の繁華街である銀座の並木通り沿いに、「鮨 新太郎」はあります。 かつては、多くの書店や出版社が立ち並ぶ神田神保町に店を構え、食通としても知られた小説家の開高健氏をはじめとする文壇文士が足しげく通っていました。銀座に店が移ってからもご贔屓は変わらず、ご主人の繊細な手捌きから次々生み出される鮨に、誰もが舌鼓を打ちます。その立ち姿と丁寧な仕事は、古き良き時代の凛とした空気をまとい、すべてに江戸前鮨の伝統を感じることが出来ます。
今回はお料理を頂きながら、ご主人に鮨職人としての「仕事」についてお話を伺いました。

ご主人の 斎條 真一(さいじょう しんいち) 様
私は東京で育ち、釣りが好きで子どもの頃はよく東京湾や多摩川に行っていました。当時、昭和30年代の前半(1955年頃)で、まだまだ食糧事情が良くありませんでしたから、釣れた魚を近所に配るとみんなが凄く喜んでくれましてね。夏場だとハゼがたくさんとれて、子どもですので唐揚げとか簡単なものしか出来ないのですが、「しんちゃんの作る唐揚げが一番おいしいねぇ。」なんて言ってくれて。自分の作ったもので人が喜んでくれるというのは嬉しいものですよね。今考えると、その頃の記憶が後にこの道へ進むきっかけになったかも知れません。
それで、仕事を考える時期になって、人が喜んでくれる仕事で自分が出来る事は料理なんじゃないかと思い、日本料理の煮方(にかた)をしている義理の兄を頼って、料理の勉強をしたいとお願いに行きました。ですが、年齢を聞かれて、「日本料理を目指すには今からじゃ遅いよ。」とあっさり断られたんです。そのとき、十九歳でした。当時、兄はすでに多くの経験を積み、日本で五本の指に入るような煮方だったんです。それで、年はどうしようもないし、諦めるしかないのかと思ったのですが、「でも、お前に本当にその気があるのなら、単品(鮨や天ぷら、蕎麦などの専門職)であれば、勉強したらいいんじゃないか。」と、なんとか受け入れてもらえることになったんです。

おまかせのお料理。左より:
車エビの焼き物とフグ皮ポン酢、冬が旬の青森産ヒラメの刺身、函館産生ウニは、がごめ昆布を食べて育ったという希少なものだとか。
 表大門(赤門)
表大門(赤門)
どんな道でもそうですが、楽をして一人前になれるなんてことはありません。それに、教える方は自分の時間を割いて手間を掛けているわけですから、優しく手取り足取り教えてもらえるなんてこともありません。怒鳴られたり、言葉より物が先に飛んで来たりなんてことはしょっちゅうで、下駄が飛んで来たこともありましたよ(笑)。時には厳しい修行に耐え兼ねて、店を飛び出したこともありましたが、私は早くに両親を亡くしていましたから、帰る家がなかったんです。それで、出て来たのは良いけれど、どこにも行くところがなくて結局先輩に電話をしたら「ばかやろう!早く戻って来い。」と。 今思うと、その時に帰る家がなかったことが幸いしたと思います。もしあったら、諦めてしまっていたかも知れません。 でも、厳しい環境に身を置いて鍛錬を繰り返すことで、仕事の技だけではなく苦難を乗り越える力が養われ、いつか本物になる為の根幹が出来上がって行くのだと思います。
それからやっと独立して、神田神保町にお店を出したのが昭和46年(1971年)。そこでは28年間営業していたのですが、街の再開発のために移転することになりました。それで色々お店の物件を探して、銀座のこの店に落ち着いてからもう15年。独立してからも大変なことはもちろん沢山ありましたが、いろんな方に可愛がって頂いてここまで続けられています。
そんな私ももう来年は七十になりますが、大きく変わって行く時代の中でその時々の厳しさを経験して来たことが、今に繋がっているんじゃないかと思いますね。

番茶で柔らかく煮上げるタコは神奈川・佐島産。きめ細かな舌触りの茶碗蒸し、〆サバの焼き物と続きます。

昭和46年の開業以来、今日まで仕入は一度も人に任せたことがありません。42年間、毎日自分で築地に通っています。自分がきちんと目利きをした納得の行く魚だけをお客様にお出ししたいという気持ちは絶対ですし、ずっと変わりません。全国から集まって来る魚介類の中から本当に良いものを見抜くには、毎日市場へ足を運んでいなければわからないことがあると思います。選んでいる間に、どれから仕込むかという段取りも出来ますしね。
ある日、市場を歩いていたとき、普段買い物をしていないのですが、たまたま通りかかったお店のおとうさんに声を掛けました。すると、その方は私の顔を見るなり、「あなた、古いですねぇ。私の父の代からですもんね。」とおっしゃるんです。お年は私と同じくらいでしょうか。続けて、「私も父の手伝いをしていた頃から長年ここで仕事をしていますが、あなたみたいに何十年も通っている人はまずお見かけしませんねぇ。嬉しくなりますよ。」と。お話したのはその時が初めてでしたが、古い人がどんどん減っていく中でそんな方がまだおられたというのは私も嬉しく思いました。
でも、何十年と築地に通っていても知らないことはまだまだありますし、教えられることもたくさんあります。そういう新しい発見に終わりがないというのも、この仕事の面白いところですね。

三重県産マグロ・大トロの漬けは大根おろしと山葵をたっぷりつけて。焼きハマグリ、優しい甘さの玉子焼き。

ひとつひとつ丁寧に仕度をされた、酢〆のコハダ。
うちの定番の品として、私は一番先に(酢〆の)コハダをお出しします。コハダは年中仕入れることが出来ますし、高級な魚ではありませんから、大衆店でも高級店でもそのお店の味付けが出来る魚じゃないかと思います。鮨は元々屋台で始まったとされていますが、その屋台が出来る前の江戸時代には、コハダ専門に「コハダや~コハダ」という掛け声と共に天秤を担いで売り歩いていたそうですから、そういう意味では江戸前鮨の原点と言えます。
そのコハダをうちの味に仕上げて、最初にお出しするようにしているのは、「うちの酢加減、塩加減はいかがですか?お口に合いますか?」と、言葉ではない会話でお客様に私の仕事をみて頂くということなんです。それがうちの定番として知って頂くようになって、よく来てくださる方にも最初にお出ししないと「あれ?何で今日はコハダが最初に出て来ないの?」って言われるんですよ(笑)。

名物、穴子の白焼き。スダチと塩でいただきます。
それから、穴子の白焼きもうちの定番のひとつになっていますが、穴子についてはこれまで本当に色々な料理を作って来ました。その中で、やっぱりこれが一番だとお客様に言って頂けるのが、この煮穴子の白焼きです。でも、定番になったのは良いんですが、穴子の旬は梅雨から夏にかけてですから、他の時期には仕入れに気を使いますし、仕度にも苦労しますね。

ここに飾ってある色紙は開高先生が書いてくださったものなんですが、神田神保町に店があった頃、とある出版社の編集者さんに連れられて初めて来て下さいましてね。その時に先生は、初めのひとつを口に入れると、「このコハダ、違うね。・・・美味いなぁ。」と。それから、穴子を召し上がって「このアナゴも美味いねぇ・・・。」とおっしゃって、次々に食べて下さったんです。最後には、「この味、日本一やね!」とまで言って下さって、非常に感激しました。その時、一番とかそういうことではなくて、先生にそんなふうに喜んで貰えた事が本当に嬉しかったですね。
※ 開高健(かいこうたけし)・・・1930-1989。大阪市出身の小説家。「裸の王様」で芥川賞、「玉、砕ける」で川端康成文学賞受賞など。釣師、食通としても広く知られ、各テーマの出版も多数。新太郎の店内に飾られた色紙には、「入ってきて 人生と叫び 出ていって 死と叫ぶ」と書かれてある。

握り:コハダ、昆布〆のヒラメ、赤貝とイカ。
それから先生は東京にいらっしゃる度に必ずうちに来て下さるようになって、座る席はいつも決まっていました。ある時、先生と一対一になって鮨をお出ししていたんですが、私が握って出すでしょ。それで、次の鮨を握ろうとして手を戻したらもうお皿に無いんですよ。あんまり早いから、先生に「飲み込んでるんじゃないですか?」って言いましてね(笑)。そうしたら、「鮨は早く食べなあかん!」っておっしゃって。あまりに早いので、急いで握っても間に合わなかった、なんて事がありました。先生は日本だけではなく、世界中の取材した先々で色んな料理を召し上がって来られて、鮨のことも本当によく知ってらっしゃいましたね。

握り:マグロの赤身、煮ハマグリ、細巻き。
長年同じ仕事をするということは簡単なことではありませんが、長く続ける間に出逢えた人々が、今の私を支えて下さっています。ですから、いつまで続けられるかはわかりませんが、みなさんが応援して下さるので、これからも頑張って握り続けたいと思っています。
■店舗情報■
鮨 新太郎|東京都中央区銀座7-5-4 並木通り 毛利ビルB1F|電話03-3574-9936|定休日 日・祝|http://www.sushi-shintaro.jp
檜のカウンター越しに、ご主人の長きに亘る経験によって完成された「仕事」が何もかも見えます。 お鮨に合うよう選ばれたお酒と器。丁寧に仕度されたネタの数々。役者が揃うと、ご主人は流れるような手捌きでお鮨を仕上げ、最高の状態でお客様にお出しする。そして、小気味良い会話と、女将さんのさり気ないおもてなしが華を添えます。 コハダをひとつ口に入れると、ご主人の心がふわりと沁み込んで、幸福なひとときが忘れられない記憶に変わっていくような気がしました。
(2014年1月取材・文 島田優紀子)
*次回の「賢人の食と心」も是非ご期待ください。