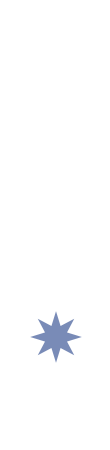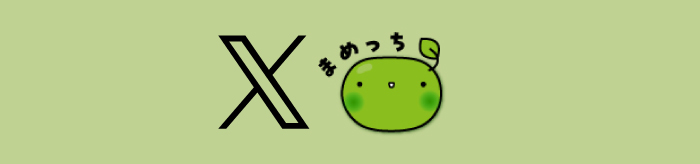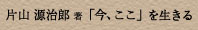麸嘉
侘びさびを重んじる京都の伝統文化が生んだ「生麩」。情緒ある味わいは、口にするたび日本人の心を静かに揺さぶります。生麩専門店として150年以上の歴史を誇る老舗「麸嘉(ふうか)」では、職人による手仕事が健在。手間を惜しまず慈しみながら作られた生麩には、作り手の誠実な心が滲んでいます。

麸嘉(本店)
京都府京都市上京区西洞院椹木町東裏辻町413 075-231-1584
http://www.fuka-kyoto.com/
慶応年間創業の京生麩の専門店。専門店としては最古で、京都御所に生麩を納めていた記録も残されている。現在は受注生産で、井戸水を使った職人による手作りにこだわる。生麩は伝統的な味のほかに、季節の食材を練り込んだものも製造。匠の技が生きる細工麩には四季の彩りが添えられ、目でも楽しませてくれる。こしあんを生麩で包み笹の葉にくるんだ麩饅頭は同店が発祥。いずれの商品も本店では販売を行わず、錦店他で購入可能。
生麩作りの朝は早い

生麩作りは、深夜からはじまります。
夜もすっかり更け、街が寝静まる深夜1時半ごろ。生麩の老舗「麸嘉」の1日は慌ただしく始まります。早出の職人が仕事場の灯りをともすと準備を開始。まだ日が昇りきらない早朝4時には職人たちが全員そろい、息を合わせて作業を進めていきます。麩嘉の生麩は手作りが基本。長く伸ばした生地にぐっと視線を寄せ、空気が入っていないか細部までチェック。リズムよく秤に乗せて生地を計量すれば、同じ目盛りにぴたり。体で覚え込んだ動きに一切の無駄はありません。時折響く威勢の良い声が活気と緊張感を高め、工場全体が次第に熱を帯びていきます。「もうそろそろええんちゃうか」。生麩作りの指揮を執る7代目小堀周一郎さんが職人の1人に声を掛けました。大きな蒸し器の扉が開き、一瞬視界をさえぎるほどの湯気がふわり。木枠から素早く取り出し水に放して冷やすと、艶やかでみずみずしい生麩の出来上がりです。
もっちりとした歯ごたえと滑らかな口当たり。出来立てをそのまま刺身のように食べてもよし、時間が経って締まったものを煮物や蒸し物にしてまたよし。生麩は調理方法によって幾通りにも味わいを深める名脇役です。
昔からの手作りを貫く思い

小麦粉から取り出したグルテンにもち粉を加えて作る生麩。シンプルでいて、実に奥の深い作業です。
その日に売るものはその日のうちに作るのが麸嘉の生麩。卸先は京都の老舗料理店が中心で、一部のデパートにも納めています。毎日電話で注文を受けて作る受注生産なので、仕込む量は日によってまちまち。特に忙しいのは、京都の観光シーズンや年末年始で、職人たちは朝から気が休まる暇もありません。それでも、生麩に練り込む梅肉は手で丁寧に裏ごしし、ぎんなんやごまもホーローの鍋で丁寧に手煎りします。頑なに手作業を貫くのは、ものづくりへの揺るぎない信念があってこそ。「よく、すべて手作りでたいへんですねと言われるんですが、やっている本人たちに特別感はありません。うちではこれがずっと当たり前やし、昔はどこの店もこうやって作っていたんですから。作業はショートカットしようと思ったらなんぼでもできるんですけど、効率ばかり追い求めても仕方ないんやないかなと。うちのやり方を手間がかかっていると見られてしまうことのほうが寂しいですよ」と小堀さん。先祖代々大事にしてきた作り手としての原点に想いを寄せます。
近所の料理屋には職人たちが毎日1軒ずつ出来立てを配達して回るのも、昔から変わらない麸嘉の日常。「配達で料理人と顔をつなぎ、硬さや味の要望を聞いてくるのも仕事のうち。納め先を知るのと知らんのとでは仕事に対する心構えも変わってきます」。毎日忙しい生麩作りを支えるのは6人の職人たち。10年働いてようやく一人前と言われる厳しい世界。職人になりたいと熱意をもって門を叩く者ばかりではなく、案外気軽に入る人も多いそう。中には、サラリーマンやフランス料理人経験者、元自衛隊員といった異色の経歴を持つ人も。地方からやってきた学生アルバイトも製造の一端を担わせ、働きながら京都を感じてもらいたいというのが、小堀さんの思いでもあります。
職人の手が生み出す味とは

生地は木枠に入れて蒸していきます。この道具も伝統の味を出すのに欠かせないもの。
生麩の主な材料は小麦粉、もち粉、水。麸嘉では小麦粉はオーストラリア産や北米産を使用し、グルテン含有率が一番高い強力粉に中力粉をブレンドして食感にバランスを持たせています。もち粉は滋賀県産や宮城県産など、国内産のものを厳選。出来上がりの状態や気候などを読みながら日々使い分け、「形をしっかりつけてほしい」「食感が硬いほうがいい」といった料理屋の細かな要望にオーダーメイドで応えられるのは手作りならではです。
生麩作りはまず、小麦粉に塩と水を入れて、生地を練るところから始まります。練り終えた生地はしばらく寝かせておいて、ある一定の時間が過ぎると水洗い。するとでんぷんが溶け出しタンパク質だけが残り、生地は濁りを帯びた色に変色します。これが主原料となるグルテンです。グルテンにもち粉を加えていくと次第に白い生麩の生地に。重量を均一にした生地を細長い木枠に入れて蒸し、水で冷やして粗熱を取ったら完成です。

急激に冷やすとグルテンが固まってしまうので、年間約15度と安定している井戸水が重宝するそう。
作り方も材料もいたってシンプル。しかし、実は奥が深いのが生麩づくりです。何十年とこの仕事と向き合ってきた小堀さんでさえ、毎日同じものを作ることはできないと言います。「生麩作りに大事なのは、生地を練るタイミング。練り過ぎるとぼぞぼそになってしまうので、一番良いタイミングを見極めるのは手の感覚が頼りです。感覚は人から教わるわけではなく、職人が個々に長年の経験の中で培っていくもんで、味や食感にも微妙に影響します。毎日作っていても、なんで今日の生地はこんなにやわらかいんやろと疑問に思ったり、いろいろとわからないことも出てくるもんですよ」。手に触れる生地の感覚が変わってきたら、配合を変えたり材料の見直しを行うのも、安定した味を生み出す秘訣。「もち粉も作物なので、毎年同じ産地で同じ状態のものが収穫できるとは限りません。ここの地域のものを使うと決めてしまうと、結局味や食感を追求できていないことになります」。素材を吟味することも職人の大事な仕事の一つです。
「麩饅頭」が誕生したのは

職人達の手際は見とれるほど鮮やか。「手際が良くないとすっきりしたものはできない」と小堀さん。
粟(あわ)のプチプチとした食感が楽しい粟生麩や、自然の蓬(よもぎ)を加えて、香りと鮮やかな色を加えた蓬生麩は昔からの伝統的な味。このほかにも麸嘉では毎日数々の商品が作られています。
その代表格が麩饅頭。観光客にも人気が高く、今では京都を代表する銘菓の一つに数えられています。しかしその歴史がまだ浅いことは、意外と知られていません。麩饅頭が誕生したのは、実は明治天皇のご発案。もともと麩がお好きだったことから、命を受けて麸嘉が作り、献上したのが最初と言われています。1つずつ手作業で丁寧に包まれた笹の葉を解くと、生麩の生地に川海苔を混ぜてほんのりと青味を帯びた饅頭が顔をのぞかせます。中にはあっさりと炊き上げた丹波大納言の自家製こしあんがたっぷり。ひと口頬張ると、なめらかなあんとしっとりとした生地がつるりと喉を通り、体の中を涼やかさが駆け抜けていきます。暑い夏を乗り切る涼菓子として、明治天皇もさぞかし楽しみに口にされていたことでしょう。

こちらが、グルテンをふかし、味をつけて油で揚げた利休麩。見た目も肉にそっくり。
ふと仕事場の隅に目をやると、気になる茶色の丸いものを発見。これは何かと小堀さんに尋ねてみました。「グルテンをふかし、しょうゆ、みりん、昆布だしで炊いたものを油で揚げたもので、精進料理などで使われる肉の代用品です。下味がしっかりとついているので、脂抜きをしてそのまま食べたり、白和えに入れたりすることが多いんですよ」。見た目はまるで肉の塊。ひと口食べてみると弾力があり、その味わいは独特。味気なさを感じがちな精進料理の中で、満足感を与えるために生まれた食材なのだそう。ここにもまた、日本人ならではの食への感性や知恵が活きています。
生麩が京都で親しまれたわけ

良質な水が豊富にあってこその、生麩作りです。
生麩は日本で親しまれ発展した食べ物ですが、そのルーツをたどると中国にたどり着きます。なぜ日本に伝わったのかは諸説あり、一説には南朝時代に南宋滅亡期の混乱を逃れた禅僧たちにより広まったとも言われ、精進料理や茶懐石に重宝されるようになりました。特に製造が盛んだったのは京都と加賀。日本人の口や料理に合うよう試行錯誤が重ねられ、明治時代に入ると一般の食卓にものぼるようになります。京都に麩屋町と呼ばれる界隈があるのは、かつて麩屋が軒を連ねていたことに由来するとか。それほどまでに京都で生麩が受け入れられたのには、宗教の影響が大きいと小堀さんは解きます。「生麩は主張の少ない食材です。仏教的思想の中に組み込まれた食材は、豆腐や湯葉も同じく、決して前に出すぎるものはいけないとされていたのでしょう。淡々と生きるという教えが食にもつながっているのではないかと思います」。

麩饅頭は笹で包む最後の工程へ。女性スタッフの手により、一つ一つ丁寧に作られていきます。
また一方で、京都は良質な地下水に恵まれた地だったからこそ、澄んだ味わいの生麩が生まれて人々に愛されたという見方もあります。小堀さんいわく、生麩は7割近く、麩饅頭にいたっては7割以上が水でできており、水の質がそのおいしさを左右するといっても過言ではありません。麸嘉では水道水には一切頼らず、昔から敷地内にこんこんと湧き出る井戸水を使用しています。「素材の一つとして使うのも生麩を冷やすのも、うちは必ず井戸水。京都で作る食べ物に地元の水を用いることで、京都でしか食べられない味を出しています」。仕事場では手を洗ったり調理台を清潔に保つのにも使われ、小堀さんが「これがないと生麩は作れない」と言い切るほど、なくてはならない存在です。
精進料理の味と精神を世界へ

本店では販売を行っていません。購入は、錦市場内の錦店他にて。
小堀さんの父親である6代目小堀正次さんは、伝統に斬新なアイデアをプラスすることに臆することなく取り組んできた人でした。1988年にはアメリカのニューヨーク・タイムズに全面広告を出し、麩への関心が高まってきた外国人へ正しい理解を促したことも。当時は大きな反響があり、本店へも多くの外国人が訪れたといいます。基礎となる味や製法は老舗としての考えを変えず、そのほかは思うようにやるのが正次さん流。その志を受け継いだ周一郎さんも、伝統の世界に一石を投じます。それが、2007年にニューヨークでオープンした精進料理の店「嘉日」です。
「ニューヨークには20代のころに行ったことがありました。たまに日本食が恋しくなって和食店に入っても、当時は中国人や韓国人が経営している店がほとんど。冷凍うどんや奇抜な見た目と味の寿司が出てきたりと、世界的な都市でもこんなもんかと正直がっかりしました」。和食文化が歪んで伝わっていく現実を、小堀さんはどうしても見過ごすことができませんでした。ニューヨークで受け入れられれば和食に対する世界の見方も変わるはずという考えと、新しいものを発信していきたいという思いに火が付き、本格的な精進料理の店を海外で初めて形にします。
料理人は京都で修行を重ねた新進気鋭の若手たち。ニューヨーカーの舌に媚びず、地のもんを使うという習慣に習い、西洋野菜を京風の味に仕立てるスタイルを貫きました。器の多彩さも和食の魅力。割れても使う日本の文化や精神も伝えたいと、金継ぎした器も食事に彩りを添えます。評判は瞬く間に広がり、世界中のシェフも注目する名店へと急成長。オープンわずか半年でミシュランの一つ星に輝き、翌年は二つ星をもらう栄誉を勝ち取りました。
冷静に時代を読むことの大切さ

本店は動乱に巻き込まれ何度か焼けていますが、建物の土台となる石は現存。昔はこの石の上に生麩を置いて売っていたことも。
嘉日が成功した理由を、小堀さんはこのように読んでいます。「もともとベジタリアンの多い国で専門店もたくさんあるのに、残念ながらどこもおいしいとは言えません。食事が終わっても満足感がなく、生きている喜びを感じられないというか。おいしいと思って食べないと、結局野菜にも失礼でしょう。そこへ私たちが提案したのは、野菜料理ってもうちょっとおいしい食べ方があるよ、野菜だけでも肉や魚を食べたときと同じように満足できるよということやったんです。だから受け入れられたんでしょうね」。
次なる目標はやはりニューヨークで生麩専門店を?「いや、それはないでしょうね。生麩の専門店ができるほどの需要は今のニューヨークにはありませんよ」と冷静な返事。嘉日は、食を通して日本の文化を世界へアプローチできるかという一つのモデルケースとして取り組んだに過ぎず、経営的な成功や発展はオープン当初からビジョンにはなかったと言います。自身が家業を継ぐと決まったときも、継続することにはさほど重きを置いていなかったとあっけらかん。「たとえば自分の子どもが8代目を継ぎたくないと言えばそれでいいし、うちの商品がいつか料理屋で使ってもらえなくなっても仕方のないこと。必要がないと思えばなくなるのは自然なことだし、無理矢理にでもしがみつかなあかんとは思ってないんです」。時代の風を読み、老舗の看板に気負うことなく進んでいく姿勢が、明日の麸嘉を作り上げています。