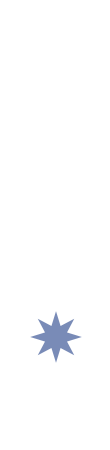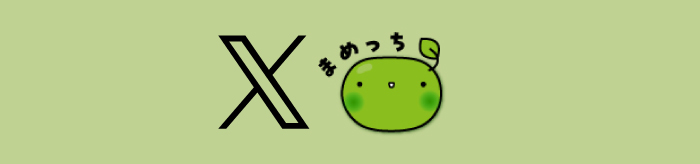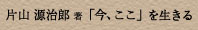京つけもの 赤尾屋
日本最古の加工食品とも言われる漬物。その起源をたどれば、縄文時代にまでさかのぼるとか。生では食べにくい野菜も漬物にすることで旨みが増し、塩分に注意しながら食べると健康増進も期待できます。今回は圧倒的な人気を誇る京漬物に焦点を当て、伝統製法で味を守り続ける店を紹介します。

京つけもの 赤尾屋
京都市東山区本町7丁目21番地 075-561-3032
http://www.akaoya.jp
宮内省の御用を務めたこともある京漬物の老舗。1699年(元禄十二年)に初代が京都の大黒町に酒造業を構えたことに始まる。1855年(安政三年)より下京区堺町五条上ル俵屋町にておいて漬物商を営み始め、その後、安政の京都大火、禁門の変による京都大火による2度の類焼のために、1865年(元治二年)に現在の場所、三十三間堂の西隣に移す。独自の製法は一子相伝で絶えることなく、現代に受け継がれている。素材となる四季折々の野菜は、優れた目利きで選別。合成着色料や合成保存料を使わず、素材本来の味わいを活かしながら一つ一つ丁寧に手仕込みしている。
漬物の里、京都を訪ねて

ごちそうが続くと、なぜだかふと簡素なごはんが恋しくなります。そんなとき、無性に食べたくなるのが漬物。たくあん、ぬか漬け、しば漬け、粕漬など、バラエティに富んだ味を丁寧に皿へと盛り付け、あとは炊き立ての白いごはんがあれば、いつもの脇役も立派な主役格です。
漬物と聞いて真っ先に名前が挙がる地と言えば京都。京都には現在200店以上の漬物屋があり、名所巡りの道すがら、ふらりと立ち寄るのも楽しみの一つです。漬物のおいしさの秘密と作り手の心に触れようと訪ねたのは、京漬物の老舗中の老舗「赤尾屋」。三十三間堂の西隣に本店を構え、今年で創業316年を迎えます。「京都やったらどこの家庭でも1、2軒は馴染みの漬物屋を持ってはるんやないですか。うちにも長い間通ってくれはる常連さんがちらほら。中にはぬか漬けの漬け方を教えてほしいと訪ねて来られたり、自分で漬けた梅干しの調子を見てほしいと、大きな容器を抱えてやってくる人もいてはりますよ」とにこやかに話すのは、十五代目の土田智史さんです。

「ご試食はいかがですか」と差し出された味は、昔ながらの馴染みのものから、アレンジを効かせたサラダ感覚のものまで彩り豊か。同じ野菜を使っていても店ごとに創意工夫が垣間見えます。トマトやかぼちゃといった意外な食材も、和の食卓に馴染むように味付けされていて、日本が誇る保存食はここまで進化したのかと驚かされることも。
造り酒屋から漬物屋へ

赤尾屋秘伝の奈良漬。こっくりと深い色に染まった瓜は味がしっかりと馴染んでいます。
赤尾屋の前身は造り酒屋でした。「酒粕がたくさんあったので、そのころから粕漬を作っていたと聞いています。昔は冷蔵庫がなかったし、奈良漬やらっきょう漬、梅干しといった常温でも長期保存のできる食べ物が重宝がられていました。うちに詳しい記録が残っているわけではないので正確なことはわかりませんが、粕漬から徐々に手を広げて今の漬物屋に至っているんやと思います」。当時から作っている奈良漬は、今も根強い人気を誇る看板商品。現在は上質な酒粕を自家発酵させ、先祖伝来の漬け方でじっくりと味を育てています。深い琥珀色に染まったうりをいただいてみると、酒粕の香りが芳醇でなんとも上品。肉厚で食べ応えがあり、シャキシャキとした食感と甘さは、お酒の肴にもごはんのお供としても申し分はありません。
こちらでは奈良漬を筆頭に、季節商品も含めるとアイテム数は60~70種類にも及びます。「僕が小さい時からうちの店にはこれくらい漬物が並んでいるんが普通やったんですけど、お客さんには『ほんまに多いなぁ』とびっくりされます。味のバリエーションも他の店と比べると多いみたいで、きゅうりの浅漬けだけで3種類も仕込んでいるところは珍しいんやないですかね」。商品はお客さんの要望から生まれたものもあれば、自分たちのアイデアを形にしたものもあり、いつのまにか増えていったのだとか。
漬物に向く野菜選び

店を訪れると出される試食の数々。涼やかな色合いと豊かな味わいに手が止まらず、完食する人もいるそう。
「漬物にしたらおもしろそうと思った野菜があれば、まずはその野菜が京都に常時入荷するものかどうかを中央市場に行って聞くんです」と智史さん。産地や農家は近郊に限らず、漬物に適した品質であれば遠地の野菜も使います。「たとえば、千枚漬用の聖護院かぶらや夏の味覚である山科なすなどは京都ならではの野菜なんでね。京都産やないとあかんもんはこだわって仕入れて漬け込みしてます。でも漬物用の野菜にはそれぞれに適したサイズや質があって、白菜漬のような通年商品は、春先の暖かくなり始めたときは長崎産、夏の暑い時期は涼しい信州産のものと季節ごとに産地を移していくんです」。きゅうりも大きく育ったものは漬物には不向き。見栄えはしても種の部分が大半を占め、パリパリとした食感が損なわれ、水分が多くて水臭く感じてしまうために商品にはなりません。素材選びにも確かな目利きが必要です。

十五代目の土田智史さん。「先祖が生んできた今の味があるからこそ、お客さんに喜んでもらえます」と胸を張ります。
智史さんは概念にとらわれず、これまでさまざまな野菜を漬けてみたそう。特に印象に残っているのは、ラディッシュと小松菜。「ラディッシュは色が鮮やかで見るからに食欲をそそるやないですか。うまくいけば商品化できるなと思ってトライしてみたんですけど、漬け込むうちにどんどん色素が抜けてしもて。せっかくのきれいな赤が、何度やっても真っ白になってしまうんです。見た目がダメなんはまず売りもんにはなりません」。一方、小松菜はというと「そこそこ上手に漬かったし色も良かったけど、もし小松菜を胡麻和えにしたもんと漬物にしたもんを一緒の食卓に並べたら、僕やったら手が伸びるんは胡麻和えの方やなと思ってしまった。野菜やったら大抵は漬物にできますが、見た目や味が適さんもんも多いんやなってことを試してみて思いますね」。一筋縄ではいかない商品開発。それでも好奇心を持ってチャレンジすることを智史さんは大事にしています。
手間をかけて味を磨く

三十三間堂の近くにある本店。接客したり商品を並べたり配送したりと、店は家族総出で切り盛りしています。
赤尾屋の漬物は合成保存料や合成着色料は使用せず、ナチュラルな色や風味が持ち味。丹精を込めて少しずつ手仕込みする技術は、親から子、孫へと一子相伝で受け継がれてきました。作業場を取り仕切るのは、智史さんの父と兄。忙しい時は智史さんもサポートします。大根の皮むきからみじん切りまですべて手作業で行うのが、創業以来貫いてきたスタイル。香りを添えるゆずは、皮の裏にある苦みの出やすい白い部分をきれいに取り除き、黄色い部分だけをみじん切りする手間を惜しみません。
また漬物づくりは「下漬け」と呼ばれる塩漬けの後、漬け替えを1度行うところが多いなか、こちらでは2度も漬け替えをしています。このひと工程を加えることで、野菜の持つ水分が十分に出切って旨みが引き出されたり、調味液が浸み込みやすくなり、味の変化を防ぐことにもつながっているのだとか。「2度の漬け替えでゆっくりと時間をかけて塩度を抜いていくことで、おいしい漬物に生まれ変わります」。さらに、塩漬けの際の塩分濃度をあえて高めに設定していることにも理由がありました。「季節や野菜によって違ったりしますが、うちでは塩漬けの塩度を7~8%にしています。塩度を高めることは、野菜に潜む雑菌を死滅させる効果もあるんです」。このように手をかけることによって、漬物独特の食感や芳香が出てくるのだそう。
漬物づくりにおいて決して妥協はしたくないと智史さん。品質を落してまで看板を掲げるほど恥ずかしいことはないという言葉に、老舗のプライドが滲みます。
冬の味「千枚漬」を仕込む

店の奥にある作業場。仕事を終えた道具はきれいに整頓され、また明日の仕込みの時を待ちます。
京の三大漬物として挙げられる、千枚漬、すぐき漬、しば漬。この3つは「京もの伝統食品」の指定を受けており、京漬物の代表選手です。京都府漬物協同組合では伝統の技と味、品質を守るため、千枚漬は聖護院かぶら、すぐきはすぐきかぶらを原料としなければならないことなど、あえていくつかの基準を設けています。色、味、食感の違いは店ごとに比べてみると歴然。個性が際立ちます。なかでも千枚漬は、樽出しの日を心待ちにするファンが多い冬ならではの味覚。赤尾屋では数年前から、その仕込みを智史さんが1人で担うようになりました。寒さの深まりとともに身を締め、甘くみずみずしい聖護院かぶら。収穫のシーズンを迎えると、智史さんの忙しさにも徐々に拍車がかかってきます。多い時は1日100玉ほど皮をむき、ヘタを落す作業を朝から晩まで黙々と続けるそうです。

漬け込みに欠かせない重石は、手入れがしやすいステンレス製。重石の加減で味も変化するのだとか。
千枚漬づくりの難しさは、まずかぶらの選別にあります。仕入れたものがすべて使えるわけではなく、一玉ずつ手と目で質を確かめて、千枚漬に適したものだけを選り分けていくのです。「聖護院かぶらは9月の半ばから下旬くらいに農家さんが畑に種をまいて育てていきます。この時期はよく台風が来るので、以前はまいた種が雨風で流されてしまってダメになってしまわないか心配しとったんですが、最近は暑さのほうが深刻。晩夏に日照りが続く環境は、かぶらの成長にとって良くありません。せっかく出た芽も枯れてしまうし、地熱が冷めないので実が水分を欲しがり、中に"す"が入ってしまうんです。そうなると漬けても味が落ちてしまうので売り物になりません」。この選別作業が最も重要で、神経を使うと言います。また、千枚漬のような旬の商品は、ロスが出ないよう売れ行きを見て仕込んでいくことも大事。「それでもロスが出てしまったときは、漬け方の研究に使わせてもらってます。そうやって地道に知識や経験値を増やしておくと、後で活きてくることもあったりするんですよ」。
一子相伝で受け継ぐことの難しさ

仕込み途中の樽は冷蔵庫の中で保存。昔は木製樽が主流でしたが、衛生上の問題で今はプラスチック製に変わっています。
家業を手伝って13年になる智史さんですが、まだまだ修行の身。この道40年の父に教えを乞い、日々技の継承に励んでいます。技は目で見て、舌で確かめて盗むもの。基本の調味液についてはレシピがありますが、漬物の出来を左右する"塩振り"は職人がそれぞれに経験の中で培ってきた感性だけで行います。「父親は『塩は手でふたすくいな』と言ってさっと樽の中に振っていきます。それを僕はじっと観察して、樽に広がった塩の状態を見て分量を判断するわけです。僕らはそれをよく雪の降り具合に例え、『うっすら積もって地面(樽底)が見えるくらいやな』みたいに表現したりします。味加減は父親が仕込んだものをなめて、舌に記憶していきます」。見様見真似で覚えたやり方を実践してみても、最初から納得できる結果を出せることなどありません。

塩は赤穂産のものなど3種類を使い分け。なすの塩もみには、粒が大きめのものを使っています。
「人ぞれぞれに手の大きさは違うやないですか。父親のふたすくいと僕のふたすくいではもちろん量も違ってくるわけで、『ふぁ~っと振るんや』と言われても、その微妙なニュアンスをつかむのは簡単やないんです。毎日同じものを食べて一緒に生活している親子ですら難しいんですから、これが他人同士やったらもっと大変。だからうちでは、外から職人さんは入れへんのです」。
疑問や迷いが山積みの毎日で、励みになるのはお客さんの何気ない言葉。「千枚漬を毎年買ってくれてはるお客さんから『今年のはおいしいな』と声を掛けられた父がショックを受けてました。今年は俺が漬けてへんのにって(笑)」。一人前と認められるまでの道のりは多難でも"一歩ずつ楽しみながら"が智史さんの信条です。
若者たちにもっと漬物を

季節の野菜を使った漬物は、食卓を鮮やかに彩ります。
若い世代を中心に進んでいると聞く漬物離れ。豊かな食生活に慣れてしまった今、漬物の必要性を感じる人が少なくなっているのかもしれません。それは店を訪れる修学旅行生の声からもうかがい知ることができるという智史さん。「どうやら漬物が食卓にのぼらないみたいなんです。食べたことがないという子も珍しくありません。たぶんこの子たちのおじいさんやおばあさんは、味噌汁にごはん、漬物があればいいという世代。父親や母親も同じものを食べて育ってきた中で、漬物の味にちょっと飽きが来てしまってるんやないかと思ったりします。それでも若い子たちに試食を勧めると、みんなおいしいと言ってくれます。味を知らんだけで、一度"ほんまもん"を食べてもらえると漬物への見方も変わるんやないかなぁ」と、漬物の未来に期待を寄せます。
こうした流れは、漬物が身近な京都においても例外ではありません。培ってきた食文化を衰退させまいと、京都では2016年度から漬物を学校給食で提供しようという動きが進んでいます。これは食育の一環としての取り組み。ごはんに味噌汁、おかず、漬物といった和食の基本である一汁三菜を献立に取り入れ、和の心を育みたいとの思いが込められています。また、京都府漬物協同組合の青年部では小学校を訪問し、ぬか床教室を開催。子どもたちに自分で漬けた漬物に愛着を持ってもらい、イメージを変えていきたいというのが活動の狙いです。
日本の食文化の礎となった漬物。その繊細で滋味あふれる味を未来永劫絶やさずにいたいものです。