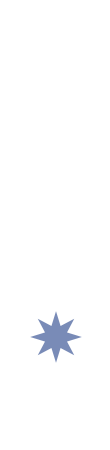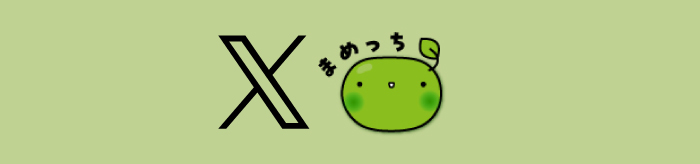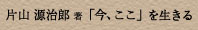三原飴店
香川県を走るローカル電車「ことでん」に揺られてたどり着いたのは、見渡す限り田畑が広がるのどかな町。緑豊かな中にポツンと駅舎だけ建つ静かな場所に、目指すべき「三原飴店」が本当にあるのだろうか…。一抹の不安を抱きながら歩いていると、突然目の前に現れたのが「ぎょうせん飴」という1枚ののぼりでした。

三原飴店
香川県高松市郊外の三木町で約300年続くぎょうせん飴の専門店。仕込みから瓶詰めまですべて手作業で行われ、昔から変わらない製法を代々嫁が守り、家内工業で営む貴重な一軒である。食べることで健やかな体をつくると言われるぎょうせん飴は、喉の炎症を鎮めたり、産後の母乳の出を助けたりするものとして食べられてきた。県内での販売は作業場に隣接する販売所のほか、市内の観光地など。ホームページからも購入でき、全国配送してくれる。
香川県木田郡三木町大字池戸3746-2
087-898-1377
https://gyousename.com
300年続くぎょうせん飴

のぼりの立つ扉を開けると、額の汗を拭いながら柔らかな笑顔で1人の女性が迎えてくれました。三原飴店の9代目を務める三原紀子さんです。今日はちょうど、ぎょうせん飴の仕込みを行っている最中だと、さっそく建物の奥へと誘ってくれました。自宅に隣接する10畳ほどのスペースが作業場。五右衛門風呂ほどの大きさのアルミ製の釜が湯気を上げ、中をのぞきこむと、白いおかゆのようなものが見えます。
「お昼くらいから炊き始めて夕方でやっとこの状態まできました。1日目の作業はだいたいここまでですが、全体の流れで見るとまだ序盤。明日も続きます」。
話す間も釜の中をかき混ぜる手は休めない紀子さん。ひたむきに仕事と向き合い、長年ぎょうせん飴の味を守ってきました。
ぎょうせん飴とは水飴の仲間。メソポタミアが発祥とされ、シルクロードを経由して日本に伝わったと言われています。飴と言っても砂糖は一切使いません。材料は麦芽、もち米、水の3つのみ。三原飴店では、讃岐うどんにも使用される小麦品種「さぬきの夢2009」から作った麦芽と広島・香川産のもち米を使用し、丹精込めて仕込むことで自然の甘みを引き出しています。
三原さん一家がぎょうせん飴を作り始めたのは、今から約300年前のこと。江戸享保のころ、丸亀藩の足軽だった祖先が阿波の国(徳島)で技術を習い、副業として取り組むようになりました。副業だったため主人は作業に携わらず、嫁の仕事として定着。以来今日まで、三原家では嫁いできた者が技術を受け継ぎ、技を大事に守るため家内工業を貫いてきました。材料も作り方も300年前とほぼ変わらず、昔ながらの味を届けています。
体力勝負の仕込み作業

おかゆ状に炊きあがったもち米を混ぜる作業は女性にとって重労働。腕や腰にも負担がかかります。(画像上)。
粉にした麦芽を少しずつ鍋に加えて、徐々に糖化を促していきます。深みのある甘さになるようにと愛情を込めて。(画像下)。
三原飴店のぎょうせん飴は、冬季は週に1度、夏季はだいたい2週間に1度のペースで作られています。仕込みにかかるのは2日間。時間をかけて甘味を育て、手間暇を惜しまないことが伝統の味を生む秘訣です。
1日目の作業は、まず釜に水を入れ、沸騰したところへ洗っておいたもち米を投入。焦げないようにゆっくりと混ぜながらもち米を炊きます。この段階では粘度が高く、鍋の中で対流しないため、火加減に注意しないとすぐに焦げてしまうので油断はできません。もち米に火が通ったら火を止めて蓋をし、蒸らします。その後温度を下げながら、細かく砕いた麦芽を少しずつ加えていきます。この、麦芽を入れては混ぜ、入れては混ぜの作業を何時間も繰り返します。簡単そうに見えて、実はこれがかなりの力仕事。
「私が手にしている混ぜる道具は『かいな』と呼ばれるのもで、頑丈な樫の木で職人さんに特別に作ってもらっています。鍋の中がとにかく重たくて釜の淵を利用しテコの原理で混ぜるものだから、樫の木以外の柔らかい木だとすぐにポキっと折れるんですよ。樫の木でもほら、柄の部分が磨耗してしまっているでしょう」。
見ると、かいなの柄は一部分だけが凹み、ビニールテープがぐるぐると巻かれています。仕込みに必要な道具は、今ではなかなか手に入りにくいものばかり。大切に手入れをして使わなければ、次の世代へ技を渡していくことが難しくなりました。
甘さの秘密は麦芽にあり

飴づくりで重要な役割を果たす麦芽。砂糖を使わなくても甘味が出るのは、麦芽のおかげです。
ぎょうせん飴作りの要となるのが麦芽です。麦芽の酵素がでんぷん質をゆっくりと糖化させることで穀物独特の甘さが引き出されます。
「釜の中が高温のときはまだ麦芽の働きが鈍め。水を入れて温度を調整しながら、60度前後に落ち着いてくると、最も活動が活発になります。麦芽を入れるタイミングも量もきっちりとは決まっていません。その辺りは長年の感覚ですね。少々多くても少なくても、最終的にきちんと仕上がればいいので、実は細かなことはあまり気にしていないんですよ」と紀子さん。
麦芽は1年間使う分をまとめて仕込みます。まず、小麦を水に漬けて室に入れ、1週間ほど置いて発芽を待ちます。発芽したら3週間余り天日干しに。その後、乾燥機に入れてカラカラになるまで乾燥させて保存し、飴を炊くときに必要な量を粉にします。麦芽作りを行うのは決まって寒さが深まる寒(かん)の時期。夏に行わないのは、温度と湿度が高すぎてカビが発生してしまう心配があるためです。仕込みに井戸水を使っていたころは、寒のころの水質が一番麦芽作りに適していたということも、冬場に作業をする大きな理由でした。
手間を惜しまず味を育てる

繰り返し浮き上がってくるアクをすくい取ることで、より一層クリアな味になってきます(画像上)。飲ませてもらった飴汁はさらりとした甘さ。穀物特有の香りもほんのりと香ります(画像下)。
2日目の作業は朝の6時ごろから開始。一晩寝かせて甘味を増した汁を、布袋に入れて絞るところからスタートします。この作業はかなりの力が必要なので、息子の嫁の由佳理さんの手を借りて二人三脚で行っています。布袋に残った栄養たっぷりの絞りかすもムダなく再利用。野菜の有機栽培に取り組む農家では肥料として、また鶏の餌などにも活用されています。
絞った飴汁は網目の異なるザルで丁寧に2回濾し、おからのような不純物を除去。このひと手間が仕上がりの口当たりをなめらかにします。濾された飴汁は再び釜の中へ。じっくりと火入れをして炊き上げていきます。何度も鍋から浮き上がってくるアクは雑味のもと。ひしゃくで丹念に取り除き、味を育てます。
まだ煮詰まる前の乳白色の飴汁を紀子さんが紙コップに注いでくれました。一口飲んでみると、透き通るような甘さがやさしく広がり、さらりと喉元を流れていきます。なんとも滋味深く、温かな味。「これが飲めるのは作り手だけの特権です」と紀子さん。長い作業の合間の1杯が、ひとときの安らぎをもたらしてくれます。
さらに煮詰めていくと、鍋の中は目まぐるしく変化。乳白色だった液体が一瞬澄み、じわじわと琥珀色を深めて粘度を増していきます。作業場全体を甘い香りが包み込むと、ようやく艶やかに糸を引くぎょうせん飴の完成です。
「単純な作業と単純な材料で、なぜ液体の色が変化して甘くなっていくのかが未だに不思議。もう何十年も作っているのに、いつもおもしろい仕事だなと思うんですよ」。
何世代にも愛される味

2日間をかけてようやく完成したぎょうせん飴。手間暇をかけても作れる量は限られています(画像上)。
ぎょうせん飴を食べるときは箸などに絡めて。一度口にすると止まらなくなるおいしさです(画像下)。
釜いっぱいに炊き始め、最終的に出来上がったぎょうせん飴は寸胴鍋に1杯ほど。紀子さんの手作業で続けるには、これが精一杯の量です。瓶に詰めていくのもラベルを貼るのもまた手作業。紀子さんは長い竹の棒を使って、器用に瓶の中へ飴を流し込んでいきます。その甘さは穏やかで深いコクがあり清らか。すーっと舌に溶けてなんとも上品です。初めて食べたのに、思わず「懐かしい」と言ってしまう人もいるのだとか。
「人々の間に砂糖が広まるまで、甘味といえばこの麦芽糖しかありませんでした。もしかしたら日本人のDNAに刷り込まれている味なのかもしれませんね」と紀子さんのご主人は話します。
三原飴店では瓶詰めで販売するまで、プラスチック製の保存容器に入れ量り売りをしていました。長年通いつめる常連さんたちの中には今も容器を大事にし、使い込んだものを手に買いに来てくれることもあるそう。親から子、子から孫へと愛され続けているぎょうせん飴。変わらない味をお客さんに届け、喜んでもらうことが紀子さんのやりがいにつながっています。
飴作りは生活の一部

人の手で絞りきれなかった汁は機械の力を借りて。自然の恵みを余すことなく絞り出します(画像上)。
絞り用の布袋は、昔使っていたものが製造されなくなり、豆腐づくりに使われているもので代用(画像下)。
けっして楽ではない飴作りの道に、紀子さんが飛び込んだのは30年以上前のこと。 「三原の家に嫁いだときに、家族から強制されたわけではありません。でも私が継がなければそこでぎょうせん飴の歴史は途絶えてしまうでしょう。せっかく長く続いてきているのだし、手作りで体に良い物としてお客さんにも喜んでもらっているなら、辞める理由もないかなと思って。8代目は割と早く亡くなってしまったので、一緒に作業をしたのは3年弱ほど。それからは1人で飴作りをしなくてはいけなくなって、教えてもらったことを思い出しながら仕事を続けました。今では嫁も手伝ってくれるようになり、作業も少しは機械を頼れるようになって、昔と比べるとずいぶんと楽になりました」。
飴作りの仕事が一番大変だった時期は戦中戦後。食糧難で甘いものは手に入らず、漁師さんがサワラを手にやってきて「これで買えないか」と言ってきたこともあったほど、皆がぎょうせん飴を欲しがりました。当時、店を切り盛りしていた7代目は、原料の米を各自持参してもらうことで飴を製造。お客さんの声に応えようと必死でがんばったそうです。
先代たちの意志を継ぐ紀子さんも、体が続く限りは仕事を続けていきたいと言います。「今まで一度も辞めたいと思ったことはありません。もうすっかり生活の一部になっているので、辛いと思ったこともないんですよ」。
技術は次の担い手に

三原飴店9代目の三原紀子さんと(右)10代目の由佳理さん(左)。お揃いの作業着は、地元特産の保多織で作ったもの(画像上)。
紀子さんを慣れた手つきでサポートする由佳理さん。息の合った作業が大変な飴づくりをスムーズに進めます(画像下)。
10代目を継ぐ嫁の由佳理さんは、紀子さんの仕事を手伝い始めて5年目。まだまだ1人で作業を全うするには自信がないと、紀子さんの背中を見ながら体に仕事を覚え込ませています。嫁いで来たときから、私も飴づくりをすると紀子さんに宣言していた由佳理さん。地元生まれでも、実はご主人と出会うまでぎょうせん飴のことはまったく知らなかったそうです。
「でも義母がとてもイキイキと仕事をしていたので、自然と飴作りに興味を持つようになりました。300年も続くものを受け継ぐって大変じゃないの?と周囲からは言われることもありますが、気負いやプレッシャーはあまり感じていません。たぶんお義母さんが楽しそうに飴を作っている姿を、いつもそばで見ているからだと思います」。
作業に携わるようになってからは仕事の大変さを痛感することもしばしば。 「一番酷なのは夏の作業。作業場には冷房がないので、火で室温が上がって汗だくになるんですよ。体にも負担が大きく、私は初めて仕込みを手伝った次の日、腰にきてしまって(笑)。義母は平気そうにやっていますが、炊き立てのもち米をかいなで混ぜるのはかなり重くて、コツをつかむまでは大変でした。一連の作業の中で、難しいと感じるのは火加減と火を落とすタイミング。季節によって微調整が必要で、夏と冬では煮詰める時間が変わりますし、熟練の義母でさえ今でも焦がすことがあるほど。私はまだ半人前なので、お義母さんが元気なうちは頼って、一緒に楽しく仕事ができればいいなと思っています」。
磨き上げた味・技・心は次の世代へとバトンが渡され、ぎょうせん飴の長い歴史はこれからも続いていきます。
【コラム】ぎょうせん飴の味わい方
滋養に富んだ食べ物として親しまれているぎょうせん飴。産前産後や母乳の出が悪いときに口にすると良いと、妊娠中や授乳中に食べる人が多いとか。ぜんそくやせき、喉にも効くとされています。そのままスプーンや竹の箸などに巻きつけて食べるのも体に良くおいしいですが、風邪をひいて喉に違和感を感じるときは、炎症を鎮めてくれるこんなアレンジもおすすめです。
- 薄くいちょう切りにした大根に、ぎょうせん飴を大根の容量の3分の1から2分の1ほどを乗せます。
- しばらく置いておくと大根からエキスが滲み出てくるので、スプーンなどで飲みましょう。
三原家では砂糖の代わりに料理にも飴を使うそう。「魚の煮付けやきんぴらに加えると、味がしまって馴染みも良くなります」と紀子さん。贅沢な味わい方ですが、ぜひ試してみたいものです。